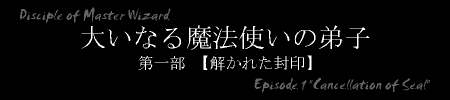
目次
【著:向野瀬 怜】
第一部 【解かれた封印】
話数 【副題】 - 作品内日付 - 文字数
プロローグ 【目覚め】 - 2057-W3-05 - 1,844
第一話 【不死の魔物 - プリーシンクト・フリーズ】 - 2058-G2-25 - 4,883
第二話 【不死の魔物 II - ピューリファイ・トループ】 - 2058-G2-21 / 2058-G2-22 - 17,146
第三話 【不死の魔物 III - 成功の定義】 - 2058-G2-25 - 8,997
第四話 【パーティキュラー・マター】 - 2058-G2-29 - 8,515
幕間一 【襲撃者と生存者と放浪者】 - 2058-G3-08 - 3,145
第五話 【対面無き邂逅】 - 2058-G3-08 - 11,327
プロローグ 【目覚め】 目次
――――逃げろ……
――――お前は、生きろ
――――…レ…を、………だろ?
その日、彼女――――システ・ルタンは目覚めた。
かなり長い時間眠った所為か中々意識がはっきりとせずボーっとベットの上から周囲を見回す。部屋に明かりは無く闇に包まれていた。
今が真夜中なのか、そもそも部屋に採光用の窓が無いのか普通の人間なら判断できなかっただろうが、彼女の視力はこの闇の中でも部屋の隅から隅まで見通す事が出来た。部屋に窓は無い。
そんな驚異的な視力を持つ彼女も流石にこの部屋は暗すぎると感じたのか一言呟く。
「……明かり」
たったそれだけの事で部屋は淡い明かりに包まれた。これなら問題無く活動できるだろう。
この明かりは彼女の魔力によって灯されたものである。
実の所、彼女なら先の一言すら発する事無く部屋を明かりで照らす事が出来たが、その辺りは彼女の気分の問題なのだろう。
光に照らし出された部屋を彼女は改めて見回した。そしてベットの傍のサイドテーブルで視線が止まる。
「……手紙」
そこには手紙があった。先程は暗さのために見落としたのだろう。
彼女の頭はまだ正常な動作を開始していない。寝ぼけているような状態である。それでも手紙を手にする。
現状把握のための情報は多い方が良い。その手紙に目を通しつつ頭の中を整理する。
――――ここが何処なのか。
(ここは水の回廊)
――――自分がどの程度眠っていたのか。
(……少なくとも一年や十年ではない、百年以上は寝ていた可能性が高い)
――――では、何故それほど眠っていたのか。
(それは、私が人々から“魔物”と言われ、封印してもらったから)
自らの記憶を探り一つずつ疑問を解消していく。
当時の人間達は彼女の事を“魔物”と呼んでいたが、彼女が人間ではないという意味ではそれは正しい。
しかし、厳密には彼女は魔物ではなかった。
彼女は恐らく最高位に分類される魔法生命体だった。魔法生命体はその名の通り、魔法によって生み出された生物だ。
彼女が生まれたのは、今から数万年も昔の事だが、今触れるべき事項ではないので詳しい事情は割愛する。
では、魔物はなんなのか? それは、一言で言うなら「人に危害を加える魔法生命体」だ。
よって、魔法生命体は厳密には魔物ではない。しかし、魔物は確かに魔法生命体だった。その事が、魔物と魔法生命体を多くの人々が同一視する原因の一つであったのは間違いないだろう。
特に、知性の高い魔物は人の味方を装って近づき、殺す。などという事をしていたので、彼女が魔物と呼ばれたのは必然だったかもしれない。
彼女は魔力で肉体を構成された高位魔法生命体。人間と見分けのつかない容姿、高い知性、強大な魔力、卓越した魔力制御能力、長い寿命……。人間にとって、敵になった時にこれほど恐ろしい存在はそうはいなかった。
結果として、彼女は人間に追われ、傷を負い、そして彼女に味方した数少ない人間の一人によって強力な封印をかけてもらい。眠りについた。
その封印は彼女を捕らえるための物ではない。いや、ほとんどの人間には捕らえるための物に写っただろうが、実際は違う。
――――彼女を人間から守るための封印だ。
そして、その彼女の味方たる人間は、彼女の封印後、人々に「ここには凶悪な魔物が封印されているから、決して近づくな」と触れ回った。
――――人間を彼女に近づけさせないためだ。
結果、彼女に百年を越える長い平穏の時が訪れた。
――――もう、彼女を知る人間は一人もいない。
彼女の目覚め。それは封印が効力を失う時だ。
彼女は知らなかった。なぜなら封印当時、彼女は大きな傷を負っていたために意識が無かったから。
しかし、彼女は知った。なぜなら手紙に大まかな状況は書かれていたから。
彼女は知っている。彼女を守ろうとした人間の多くが、彼らと同じ人間に殺された事を。
彼女を守る封印は消えた。しかし、もう一つの封印は消えない。
彼女が、彼女自身にかけた。暗示を基本とした強力な封印。――――それによって、彼女は“人間に対しては力を使えない”、彼女は人間と共存しようとして力を封じたが、結果は失敗だった。
しかも、その封印のために彼女は、人間を超える力を持ちながら人間に守られ、人間に傷つけられ、親しい人たちを守る事すら出来なかった。
彼女はしばし悩む。この誰も自分を知らない世界で何をするべきか。
「…………旅。……でもしようかな」
システ・ルタンが眠りについたのが、大陸統一暦1583年、現在が2057年。
―――――― 474年が経過していた。
第一話 【不死の魔物 - プリーシンクト・フリーズ】 目次
照明石の光の中を複数の人影が蠢く。照明石はビー球ほどの大きさの魔法具で、魔力を流し込むと発光する。魔法具の中では最も安価な部類に入る物だ。
人影がぶつかり合う度に、一体、また一体と人影が数を減らす。
その人影の一つ、サライス・レイストは戦っていた。右手に両刃の長剣を持ち、敵を圧倒的に凌駕するスピードで動き、反撃の隙を与えずに斬り裂く。が、敵が血しぶきを上げる事は無い。
「全く、歯応えが無いった、らっ!」
更に剣を一閃して人影を斬る。やはり『それ』は血を流す事なく、その場に崩れる。
サライスは既に二十歳を迎えている女性だが、その外見はせいぜい十四・五歳である。その見た目は少女そのもので「美人」というより「可愛い」に分類されてしまう。その“可愛い外見”のサライスは、その場にいる敵の四分の一程度――数にすると十体前後を既に葬っている。腰の辺りまで伸ばし一つにまとめられた黒い髪をなびかせて敵を斬る様に、違和感を拭い切れない。
黒い髪、黒い瞳、そして服装も黒を基調としたものだ。照明石の光を反射して白く光る長剣の刀身とのコントラストで、ある種美しくすらある。
【仕方ないだろう。動いているとはいえ所詮は死体だ。お嬢が遅れを取るような事は無かろう】
サライスに受け答えするのは、大きな灰色の毛並みの狼だ。名をグラストと言う。彼はサライスを上手くサポートし、戦いやすい場を作り出していた。
敵がサライスの死角に回り込むならこれを制し、必要なら排除する。いわば相棒というやつである。
「それは分かってるけど、ね!」
その言葉と共のサライスの剣が敵を斬り裂く、が今回は先ほどまでとは違っていた。
剣が斬った事によってできた傷から何かが飛び出したのだ。サライスは反射的にこれを避け、軽く距離を取る。
血だ。今サライスが斬った敵が“血しぶきを上げて”崩れ折れる。
今、サライスが相対している敵は、アンデッドと呼ばれる種類の敵だ。いわゆる、ゾンビやグールといった類の魔物である。
それらは死体が、なんらかの要因によって動いているものだ。生物というより現象に近い魔物である。要因は幾つか考えられる。死体に死者の魂が宿って云々という宗教的なものから、魔法学的な何者かが魔法によって死体を操っている、というものまで様々だ。
死体なので、当然心臓は動いていないし血は固まっている。“血しぶきを上げる訳が無い”のだ。
「グラスト! おかしくない?」
【うむ、何か別のものが混ざっているようだな】
「なんなのか分かる?」
【ふむ、少し時間をくれ】
「了解」
サライスは言葉短く答えると、敵に向かって行く。が、防戦に専念する。
正体不明の魔物には下手に手が出せない。魔物によっては厄介な性質を持つものもいるからだ。
そうしてサライスが時間を稼ぐ間にグラストが敵を観察する。こうした頭脳労働的な作業はグラストが担当する事が多い。何せサライスとグラストでは知識量でグラストの方が圧倒的に勝っているのだ。
そして、周囲を観察していたグラストの目に不自然なものが映った。それは、先ほど血しぶきをあげて倒れた魔物。より正確にはその血液だ。
グラストの目には、その血液が動いたように見えた。当然、血液が単独で動くなんて事は通常はありえない。が、相手は魔物、常識で測ってはいけない。その血液を注意深く観察する。
【っ! お嬢、下がれ!】
「!?」
サライスは突然の警告に逆らう事なく即座にバックステップで後退する。
そのサライスの目の前を赤い何かが高速で通り過ぎる。
「なに!?」
【恐らく、アンデッドスライムだ】
「はぁ!?」
その魔物の名を聞いて、サライスが絶叫と疑問を同時に発する。
「アンデッドスライムって、この辺りは生息地からかなり外れてるじゃない! スライムすら殆どいないのよ!?」
【しかし、あれはそうとしか考えられん】
「マジ? アンデッドスライムなんて初めて見たわ」
【まぁ、数がいないからな】
アンデッドスライム――その魔物は生物の体内に入り込み、その肉体を生きたまま乗っ取る。そんなたちの悪い魔物だ。乗っ取られた生物は自我を殺され、肉体的には生きたまま殺される。
そして、乗っ取られた肉体の動きは、ゾンビなどのアンデッド系の魔物の緩慢な動きに類似する。アンデッドスライムという名はそこからきた。
肉体は生きている、心臓も動いている。当然血流もある。だから、血しぶきもあがる。
「って、待って。さっきの動き、スライム系のスピードじゃなかったけど?」
【ポンプがある。それを使ったんだろう】
「ポンプ? っ、おっと」
攻撃を回避しながらの会話だ。敵の動きが緩慢だからできる芸当だ。
【……心臓だ】
「うげっ」
サライスが気色悪げに表情を歪める。周囲のアンデッドから漂う腐臭も、その不快感に拍車をかける。
「倒し方は?」
【一般的なスライムと同等】
「ちっ、魔法か」
【……お嬢は魔法使いだろう、そこで舌打ちするのは不適切じゃないか?】
「『魔法使いは研究者であれ』――先生の言葉よ?」
【……そんな事も言っていたな】
「それに、こんな地下遺跡内で下手に魔法使ったら、私たちもやばいわよ」
【魔力制御が完璧なら問題ないはずだ】
「苦手」
【……】
スライムの倒し方は幾通りかある。簡単に言ってしまうと『焼却』『乾燥』『電撃』『凍結』の四通りが代表的だ。もっと難易度を上げれば魔法による『石化』も有効ではあるが一般的ではない。
普通は『焼却』を用いる事が多い。魔法使いでなくても比較的扱いやすいからだ。
しかし、問題もある。それはスライムの主な生息地だ。洞穴の中や森のじめじめした場所や水場の近く。はっきり言って『炎』を使うのに向かない場所ばかりなのだ。特にこの場所は未探索の遺跡だ。しかも地下、下手に炎など使おうものなら、何に引火するか分かったものではない。
それに、スライムはその肉体が殆ど水分で構成されている。更にスライム系の魔物は少し存在すれば多量に存在するのが常だ。それを『焼却』によって倒す、というのは高温で多量の水蒸気が発生する事を意味する。地下遺跡という密室空間内で使えるものではない。
他の『乾燥』『電撃』『凍結』は魔法が使えないと実現が難しい手段だ。だから、スライムは『無視』するのが一番多い対処法だが、今回は倒すのが目的なのだから無視はできない。
「やっぱり、凍死させるしかないか」
【そうだな】
『凍死』という表現が適切かどうかはともかく、超低温による水分の凍結とそれに伴う細胞壁の破壊。これが、スライムに対する有効な手段である事は確かだ。
そして、『乾燥』『電撃』は魔法の中では扱いが難しい部類に入る。魔力制御が苦手なサライスがこれを避けるのは当然と言える。
「グラスト、時間稼いで」
【うむ】
言葉と共にサライスがグラストの後ろに下がる。グラストはそのサライスの動きにタイミングを合わせて前方に躍り出る。
サライスは後ろに下がると、直ぐに剣を地面に突き刺し、紐に吊るされた宝石のようなものを取り出す。
これは、かなり高機能な魔法発動媒体だ。サライス自身はこの魔法発動媒体を『クリスタル』と呼んでいる。製作はサライスの師匠、リーベルト・ファルスだ。
その機能は『やらないよりやった方がマシな程度の魔力増幅』『魔法陣展開の省略』『呪文の一時記憶(記憶した呪文を省略できる)』の三つだ。通常の魔法発動媒体が魔力制御の補助を目的に作られている事を考えると、かなり特殊な作りをしていると言える。
三つの中で最も重要なのは『魔法陣展開の省略』だろうか、『魔力増幅』は本当に微々たる物だし、『呪文の一時記憶』は記憶できる呪文の数が一つだけだ。明らかに『魔法陣展開の省略』に重点を置いて製作されている。基本的には魔法陣展開や呪文を省略する事で魔法の発動を早める事を目的としているといえる。
当然、今回のような数十体の敵に対して効果を発揮するような、大規模魔法の呪文が記憶されているはずもなく、呪文詠唱から始めざるを得ない。
サライスはクリスタルからつながる紐を左手中指に巻きつけ、クリスタル本体が自身の目の高さに来るように吊るす。
「ラナトゥル・ィエトゥルナ・ハルマー・カラ・クラ・ディラタ・アーラス!」
呪文詠唱と共に、クリスタル本体に魔力が集中する。そして、左手が徐々に下がる。
「我が魔力よ、呼びかけに答え、凍てつきし大地となり、全てを氷の彫像と化せ!!」
呪文詠唱終了と同時、クリスタル本体が地に突き立った剣の柄に触れる。クリスタルに溜め込まれた膨大な魔力が剣を通して地面に広がる。
グラストが呪文詠唱終了と魔法発動を感知して素早くサライスの後ろに移動する。
そして――――
――――大地が凍った。
地面が魔力の広がりにしたがって、次々に凍りつく。アンデッドや今は地を這うアンデッドスライムを巻き込み、凍りつく。
――――それはまさに氷の彫像だ。
今、サライスが使った魔法は魔法体系で分類するなら、『ギルタリ』と呼ばれる魔法体系によって構築された魔法だ。この魔法体系は汎用性が高く使いやすいのが特徴で、現状で最も一般的な魔法体系だ。他にも魔法行使に呪文と魔法陣を使用するとか、若干魔力消費が激しい、などの特徴もある。
サライスの魔法はほぼ全て、この魔法体系で構築されたものだ。
また、今の魔法を更に細かく分類すると、『浸透系広域攻撃魔法』というものになる。攻撃魔法は魔力の弾や炎などを直接敵にぶつける『放出系』が基本だが、それに比べて浸透系は間接的な攻撃方法で魔力を何かに浸透させる事で効果を発揮する。今回の場合、スライムというちょっとした隙間でも入り込むような不定形の魔物が相手だったので、放出系魔法では殲滅が難しい、そのため地面を通して魔法を使ったのだ。これならば、地面に接触しているものを一度に攻撃できる。
具体的には『魔力を地面に浸透させて広範囲に渡って一気に凍結させる広域攻撃魔法』という事になる。
「さ、寒い……、寒すぎ……」
【魔力制御が不完全な証拠だな。ついでに言うと無駄に出力上げすぎだ】
「仕方ないでしょ、苦手なんだから。それと、出力不足よりマシでしょ?」
【お嬢の保有魔力量がかなり多いとはいえ、それを理由に無駄遣いして良いという訳では――】
「はいはい、説教は後々」
【むぅ……】
そう言って、サライスは未だに地面に突き刺さったままの長剣の柄に手をかける。
「うひゃ、冷たい」
皮製の手袋越しに伝わる冷気に自然と言葉がもれる。
そして、それを無視して引き抜くために力を込めた時、それは起きた。
――――鳴り響く、鈍く不吉な音。
――――呆然とするサライス。
――――その手にある柄だけの長剣。
――――地面に突き刺さったままの刀身。
「折れたぁーーーー!!」
【普通の剣をあんな魔法の基点にしたんだ。想定でき得る事態だろ?】
「そんな事、言ったって! 丁度良いのがこれしか無か…………、お、おぉぉぉ……」
【そこまで嘆くか? 別にいわれのある品だった訳でもなかろうに】
「買って一ヶ月……」
【ふむ、そういえば前回は敵対した魔法使いの攻撃魔法を、刀身に無理やり魔力をまとわせて叩き切ったのが原因だったか?】
「うぅ……」
意気消沈したサライスは右手に握った柄(元長剣)を大きく振りかぶって地面に――――
「……手袋に貼りついたぁ」
地面に叩きつけようとしたが、低温状態の柄が手袋に貼りつき実現できなかった。
【……】
手袋からベリベリ柄を剥がすサライスを、グラストは黙って見つめる。特にかけるべき言葉は無い。
サライスは剥がした柄を投げ捨てると、今度は腰に吊っていた長剣の鞘も剣帯から取り外して投げ捨てる。どうも、気が立っている様だ。
そして、クリスタルを左手でしっかり握りこみ、予備として所持していた短剣を乱暴に引き抜いたところでグラストに向き直る。
「グラスト! 皆と合流するわ!」
【あぁ、その方が良いだろうな。それと――――】
「何っ!?」
【……少し落ち着け】
その言葉を無視して歩き出すサライスの姿に溜息を吐きつつ、グラストは後を追った。
第二話 【不死の魔物 II - ピューリファイ・トループ】 目次
|依頼申請書 << 緊急時用 >>
|申請日時:2058-G2-20
|依頼人:セラスターン教団
|依頼概要:アンデッドの浄化に赴く部隊の護衛
|依頼詳細
| 22日には出発するので、21日までにはメンバーを揃えて欲しい。
| 人数は最低でも5名か6名(出来れば、それ以上)。
| ※以下、詳細は添付書類を参照。
「そういえばさぁ、グラストって子供作れるの?」
これは遺跡内でアンデッド退治にいそしむ数日前の話である。ライサスル王国の“王都クラベンス”へと向かう道すがらサライスが唐突に質問した。
【……話の流れが把握できないんだが?】
「ただの雑談に流れも何も無いと思うけど……」
【ふむ、まぁ、結論から言うと分からん】
「分からない?」
【うむ、お嬢も知っての通り、我は狼をベースとする魔法生命体だ。それを考慮すると子を生すことができないと断言することはできないし、逆に狼をベースとしているとはいえ魔法生命体として既に別の生物になっているからな、子供が作れると断言もできない】
「うーん、はっきりしないなぁ」
【……元々、お嬢を知識面でサポートするためにマスターが作り出したのが我だ。生殖活動まで考慮した魔法生命体化なぞしている筈も無いだろ?】
「まぁ、確かにそう言われると、そうなんだけどね」
【まぁ、少なくとも発情期に見舞われた事は一度も無い。発情期が無いのか、それとも単に発情期まで至っていないのかは分からんがな】
「でも、グラストって生まれてから十年近く経ってるでしょ? なら、発情期があるならとっくに来てるんじゃない?」
【……そうとも限らない】
「?」
【野生の狼と我とでは、そもそも寿命が全く違う】
「うん、そうね」
【という事はだ、野生の狼のように慌てて子孫を残す必要は無いという事だ】
「……だから発情期が来るのが遅い?」
【と、いう考え方もできる。という話だ】
「うーん……」
サライスは少し考え込むと、ポツリと言葉を漏らした。
「そういえば先生って何歳なんだろ?」
【……突然なんだ?】
「いや、グラストが生まれた十年前の先生と今の先生って容姿が全く同じだなぁ。って思ったら気になって」
【……聞きたいのか?】
「知ってるの?」
【我の知識や記憶、思考パターンはマスターのものをベースにしている。我が生まれて以降のマスターの新しい知識や記憶は知らないが、それ以前のものなら知っている】
「あ、そっか。じゃ、教えて」
【……何歳だと思う?】
「え? うーん、先生の事だから普通じゃないよね。……な、七百歳くらい?」
【…………】
「さ、流石に無いよね! それは! あははっ!」
【桁が違う】
「え? 二桁? 意外と普通」
【逆だ】
「逆? 逆って……、あー…………、マジ!?」
【それを踏まえて、マスターの年齢を聞きたいか?】
「うっ……、や、やめとこうかな」
【そうか】
その後しばらく会話が消えた。ただ、サライスが時折「七百で桁が違うって、……千とか、万とか…………? あ、ありえん!」などと、つぶつぶつ言っているのが不気味ではあった。
【……そろそろ街ではないか?】
「え? あ、そうだね」
【では、我はいつも通り姿を消しておく】
「はいはい、またね」
グラストが道から外れて姿を消す。流石に狼が街中を歩いていたら大騒ぎになってしまう。なので、街に入る時にはこうして別行動を取るのが基本だ。
「さて、頑張ってお仕事探しますかね」
旅をするにも金がかかる。今回の街を訪れる目的は路銀稼ぎである。
グラストと別れてしばらくすると、流石に王都と呼ばれる都市が近づいているだけあって人通りも増えてくる。ここまで来ると王都もすぐそこである。
この王都で資金稼ぎをするわけだ。サライスの職業は彼女的には、真っ先に“魔法使い”がきて次に“冒険者”がくる。――彼女の現在の生活を客観的に見た場合、明らかに“冒険者”が一番目に来る職業なのだが、ここで語っても仕方の無い事である。
魔法使いは、基本的に魔法を研究したり、魔法を使ったりする人種の事だ。サライスのように旅をしている魔法使いとなると、当然のように“魔法の研究”よりも“魔法を使う”に比重が傾く。
そのサライスが“魔法使いとして”資金稼ぎをするとしたら、魔法を使った大道芸的なものから、攻撃魔法の破壊力にものをいわせた賞金首狩りだとか――まぁ、なんというか選択肢は多い。
しかし、サライスには師の教えとして『魔法使いは研究者であれ』というものがある。そのため、サライスはやむを得ない事態でもない限り、魔法(特に攻撃魔法)の使用は控えている。とはいえ、使うべき時には盛大に使う。それは彼女の師にしても同じ事だ。
無暗に魔法を使わない以上、魔法による資金稼ぎは選択肢から消える。
次に冒険者だが、これは十六歳以上で一定の条件をクリアした者に冒険者ギルドが発行するライセンスを所持する者の事である。
冒険者はギルドによって旅先での仕事を斡旋してもらえる。その仕事は“何かしらの物品の配達”などのものから、“魔物討伐”まで幅広い。仕事はギルドによって調整がされ、その冒険者が達成可能であると思われるものが斡旋される。そのため、仕事に失敗という事はまず無い。
サライスの場合、冒険者になって三年が過ぎており、その間それなりに仕事をこなしてきた事から、ギルドから斡旋される仕事も比較的高い難易度のものが多い。難易度が高ければ当然のように報酬も高い。サライスとしても低報酬の仕事を数多くこなすよりも、高報酬の仕事を一つこなす方が楽なので、難易度の高い仕事が紹介される事に不満は無い。
そして、冒険者ギルドは各地に支部を持っており、王都と呼ばれるほどの大都市には当然のように、その支部は存在する。
はっきり言って、仕事探しにおいて、サライスが頑張る必要は微塵も無い。ギルドの支部を訪れればそれで事足りるのだ。
「ん……と、サライス・レイストさん。お仕事探しですよね?」
「ええ」
場所は冒険者ギルド、クラベンス支部内の受付。冒険者のライセンス(手帳型)を見せる事でギルドの各種サービスを利用できる。
サービスには先に話題に出た仕事の斡旋や、旅に必要な情報の提供(情報によっては有料)などがある。
殆どの冒険者は仕事探しのためにギルドを利用する。そのため上の「お仕事探しですよね?」というセリフにつながる訳だ。
このセリフはクラベンス支部受付担当者、胸の名札によると名前はファリア・イーストイという、肩にかかるくらいの長さの赤みがかった髪が印象的な女性が発したものだ。サライスも仕事探しを目的にやって来たので肯定の意を返す。
「んー、でしたら、今、急ぎの仕事が一件あるんですが、それはどうです? 護衛のお仕事なんですが」
「詳しく聞かせて」
「ここから、徒歩三日ほどの位置にある遺跡にアンデッドが発生したという事で、これを浄化するためにセラスターン教団の高位神官を中心とする部隊が編成されまして、で依頼はその部隊の護衛です。昨日、緊急という事で依頼が来まして、冒険者数人を今日中に寄越して欲しいと、明日の早朝には遺跡に出立だそうで、時間的猶予は全くありませんね。あと、他の細かな所とか報酬とかの情報はこっちの紙に……」
サライスはその紙を受け取り目を通す。重要な部分を引っ張り出して、その上大胆に要約するとこうだ。
その間、寄ってくるアンデッドをバッタバッタとハリ倒す役目を冒険者にやらせちゃろう。
ゾンビとかと直接戦うの嫌だし〜、生理的に。
――――なんだか、かなりやる気のない説明になってしまったが、言いたい事は伝わっただろう。いや、伝わっていて欲しい、と切に願う。
もちろん本来の文章はもっと堅苦しい物であると察していただきたい。
「それと、今日の午後四時、今から三時間後くらいに依頼主の方から詳しい説明……と言うか、打ち合わせのようなものがあるそうですので……、えっと、この紹介状を……、この仕事受けますか?」
「……そうね」
ファリアの言葉を受け、一瞬考えるがすぐに答えが出る。
「受けるわ」
アンデッド相手なら手加減が必要ない。という思惑もサライスにはある。サライスははっきり言って手加減が苦手だ。
サライスの戦闘技術は(剣技にしろ魔法にしろ)基本的に“必殺”である。相手を殺さずに倒す、というのはかなり神経を使うのだ。だが、アンデッドのような相手なら、その辺、気兼ねがいらない。サライスにとっては“やり易い相手”だ。
もちろん、死体が動くという状況に不快感は感じるが、それは仕事を断るほどの理由にはならない。それに、こういった戦闘が前提の仕事は報酬も相応に高いので、そこに魅力も感じる。
……感じるし、魔法使いの観点から見れば、その“アンデッドが発生した遺跡”にも多少興味がそそられる。最下級とはいえ、魔法生命体が(自然発生か人為的かはともかく)発生するような遺跡だ。魔法使いの興味対象としては十分だ。
因みに、アンデッドは最下級の魔法生命体である。この場合の“最下級”が意味する所は、あくまで“技術面”での話であって、“強い”とか“弱い”とかとは関係ない。アンデッドというのは要するに“死体を動かすだけ”である。魔法生命体として見れば、そもそも“生命ですらない”ような低レベルな技術だ。技術的に最低レベルであるため、条件さえ揃えば“自然発生”も十分考えられる。
これは、蛇足的な話だが、高レベルの魔法生命体の条件は基本的に“高い知性”と“強固な肉体”を持っている事だ。アンデッドにはそのどちらもない。
他には“特殊な能力を持つ魔法生命体”というのも技術的にはレベルが高いものが多い。
「では、四時にこの紹介状を持って、セラスターン教団のクラベンス事務局の方に行って下さい。……それと場所は――――」
紹介状を受け取り、事務局の詳しい場所を聞けば、ギルドにもう用はない。サライスはさっさと立ち去る事にする。
「でも、三時間もどうやって時間潰せってのかしら……」
指定の時間の約十分前、サライスはセラスターン教団クラベンス事務局の一室にやって来た。受付で紹介状を見せるとそのままこの部屋に通されたのだ。
その部屋には既に男女の二人組が存在した。その服装から見てサライスと同じく依頼を受けた冒険者だろうと推察できる。教団の関係者は、まだ来ていないようである。
「な、あんなガキまで参加すんのかよっ!」
男の方のセリフにサライスは小さく息を吐く。良くある事である。
何せ、冒険者ライセンスが発行されるのは十六歳以上の人間に対してだけである。たとえ実年齢が二十歳とは言え、サライスの外見は十四や十五程度だ。“ガキ”あるいは“チビ”呼ばわりされる事はよくある。
三年前の冒険者になったばかりの頃はもっと酷かった。当時は外見年齢で「冒険者であるはずがない」と判断される事が多々あった。現在では説明なしでも冒険者である事には納得してもらえるようになってきた。だが、やはり例外なく“新人”だと思われてしまう。
そんな訳で、サライスはこういった評価には慣れている。
……慣れているのだが、
(……面と向かって言われるとムカつくわね)
良く見ると女の方も、若干驚いているようでもある。まぁ、この程度の反応ならサライスも気にならない。
「頭の中身がガキな人間に、ガキ呼ばわりされるのは流石に心外ね」
サライスは売られた喧嘩は速攻で買う人間である。こんなセリフを小声で、しかし相手に伝わるように言う事もお手の物だ。
「で、なんで私はこんなところに立ってるのかな?」
サライスは小声で誰の耳にも届かない言葉を呟く。
そのサライスの正面には先ほどの冒険者の男。直前のやり取りで分かった事だが、名前はマイスと言うらしい。三十歳に若干とどかないくらいの年齢の男だ。
マイスは顔を真っ赤にして怒りをあらわにしている。
現状を端的に説明すると、先ほどサライスと口論になり、結果口では敵わないと悟ったマイスがサライスに決闘を申し込んだ。それに対してサライスは仕事を口実にやんわり断りを入れようとしたところに、ふらりとやって来た今回の護衛対象の部隊の中心人物である所の高位神官殿の「それなら、中庭でやるといいよ。君達の実力が見れて丁度いいし」という、ありがたいお言葉により、現在に至る。
(全く、余計な事を……)
溜息を吐きつつ剣を抜くサライス。とはいえ、やる気は微塵もないのでできる限り手を抜いて勝つ事を考える。サライスは“決闘”や“戦い”に喜びを見出すタイプの人間ではない。
マイスの得物はサライスと同じ長剣。体格はそれほど筋骨隆々という訳ではないが、それなりに鍛えられているのが見て取れる。得物が同じとはいえ性別と体格の差を見るに、正面からの打ち合いでサライスが勝つのは難しい。
そうはいっても、実年齢の五歳以上も若く見られてしまうのが常であるくらいサライスは華奢な体つきをしているので、この程度のハンデは慣れている……というとちょっと変だが、とにかく純粋な力勝負での不利はいつもの事なのだ。だから、そういった場合の戦い方というのも心得ている。
サライスは剣を軽く一振りすると、不意に周囲を見回す。
(なんか、人増えてるし……)
人の見せ物になると思うとテンションは下がる一方である。と同時にこの状況に対する怒りも湧いてくるから不思議である。
(あ、なんかちょっと暴れたくなってきた)
サライスはストレスを体を動かして発散するタイプである。
そして、サライスは湧き上がる怒りを無理やりヤル気に変換して、不敵に口の端を吊り上げる。サライスの容姿にその表情は、かなりの違和感を感させる。証拠に眼前のマイスは一瞬虚を突かれたような表情をした。
その一瞬の隙を見逃さず、サライスは一気に間合いを詰めると斬撃を繰り出す。
「なっ!?」
開始の合図もなく、いきなり仕掛けてきたサライスにマイスが驚きの声を上げながらもその攻撃を捌く。
マイスの様子にサライスは再度不敵な笑みを見せる。
「実力が知りたいだけなら、別に合図なんていらないでしょ?」
「くっ! じょ、上等だ!」
マイスは最初の一手を取られた以上、隙を見て反撃しなければならないのだが、反撃の隙を与えずに繰り出されるサライスの連撃を受けるために防戦に回らざるを得ない。その上、得物が同じでも体格の差から来るリーチの差があるため、現在の位置関係はサライスが最も戦い易い位置だ。尚更、彼が反撃の隙を見つけるのは難しい。
無論、彼にしても一度距離を取って仕切り直したい所だが、スピードでも小回りでもサライスの方が上手である。普通に距離を取ろうとしても思い通りにはいかない。
サライスは剣士としては決して強くはない。元々が魔法使いである事もそうだが、体格が華奢である事からも想像できるように、力も体力も剣を扱う者としては低めだ。もちろん、同年代の一般女性に比べればはるかに優れた身体能力を持ってはいる。だが、それは男の剣士相手に対抗できる程のものではない。サライス自身それが分かっているから、合図もなしに攻撃を仕掛けて戦いのペースを握ってきたのだ。
「ちっ! やりづらい!」
一瞬前まで上半身に集中していたサライスの攻撃が、唐突に下半身を狙うものに切り替わった。下半身――足元の攻撃への対処は上半身のそれへの対処に比べて難しい。実際、上半身への攻撃に慣れてきた所に唐突に行われた、下半身への攻撃に対応できたのは、ほとんど偶然だった。
サライスはこういう、“相手の虚を突き主導権を握る事”に長けている。主導権を“握っている”のと“握っていない”のとでは体力の消費量も違ってくるし、主導権を握られてしまっては本来の実力も発揮しにくい。そのため、体力差のある相手とでもサライスは渡り合えるのだ。
純粋に剣技だけで比べたら、マイスの方が若干上だろう。しかし、サライスは剣の腕ではなく“戦い方”が上手いのだ。相手から見れば「やりづらい」という評価が一番的を射ている。
サライスの戦闘能力は実際に戦っているマイスや周囲で見ている人間たちにとって、想像以上のものだった。サライスの見た目からその実力を計るのは難しい。
「くそ、ガキのくせにっ!」
なかなか攻勢に移れないマイスが悪態を吐きながらも、サライスの攻撃を受け続ける。
そんなマイスにサライスが更に足元に斬撃を繰り出す。それをマイスが半ばルーチン化した動作で受けようとする。しかし、二つの剣がぶつかり合う前にサライスの剣の軌道が変化した。足元に向かう剣が唐突にほぼ真上に向かう軌道を描いたのだ。
そして、その軌道の先にあるのはマイスの顎だ。
「!?」
マイスはその攻撃を大きく仰け反るようにしてなんとか回避する。直後、数瞬前までマイスの顔が存在した場所を、サライスの剣が斬撃から刺突に変化するようにして通過する。もし、回避行動を取っていなかったら、喉を貫かれていた事だろう。無論、これは決闘であるので本気で殺すための攻撃ではない。サライス自身が相手が回避可能であると判断して繰り出した攻撃だ。そうは言っても、ほぼ全力の攻撃であった事は確かだし、そう言う意味ではサライスは相手の実力を認めたと言っても良い。
その回避運動によって、マイスの体勢が大きく崩れる。これは大きな隙である。
マイスは止めの追撃に対応するため、転倒しないようにバランスを取りつつも警戒を強める。しかし、追撃が来る気配はなかった。
マイスは疑問を感じつつも、体勢を立て直しサライスに視線を向ける。サライスはマイスから五メートルは離れた位置にいた。勝負を決める絶好の機会を無視して距離を取っていたようだ。
「……なんのつもりだ?」
「……別に? ただ、このままろくろく反撃もできずに終わったら、あなたが納得できないんじゃないかと思っただけよ。だから、一回だけ仕切り直してあげる」
「て、てめぇ」
「それと」
怒りに震えるマイスを遮るようにしてサライスは言葉を続ける。
「私はサライス・レイスト、二十歳、冒険者になって三年。――――ガキって言うな!!」
サライスはこの主張がしたいがために、一旦距離を置いたのだ。……なんと言うか、その言動がガキっぽい。
「……」
突然のサライスの主張に呆気に取られるマイス。
「……行くわよ」
その言葉と共にサライスが、今度は真正面からマイスに接近する。
はっきり言って、一度仕切り直してしまった分、サライスの方が不利だと言わざるを得ない。そして、それはサライスも承知している。
当然のように、今度はマイスが押す展開となる。サライスは力で劣っている為に、回避と受け流しに重点を置いて戦う。正面からまともに受けていては直ぐに押し負けてしまうのが分かり切っているから、できるだけ力押しの展開にはしたくないのだ。
逆にマイスは力で勝っているのだから力押しの展開になってもらった方がありがたい。
「っ……ち、はっ!」
「くぅ……」
仕切り直してからは明らかにサライスが劣勢だ。何せその行動の殆どが防御・回避のために行われているもので、攻撃行動が殆ど見られない。このままでは体力で劣るサライスが、いずれ倒れる事になるだろう。とは言え、防御以外に何もしていない訳でもない。機をうかがっているのだ。一気に勝負を決する事のできる“機”を……。
無論、今のマイスがそう簡単に隙を見せるとも思えないが、誰しも隙が生まれやすい瞬間というものが存在するものだ。サライスはそれを見逃さないように気を張る。サライスの体力面を見ても、恐らくは次にマイスが見せる隙を見逃せばサライスの負けなのだから……。
そうこうするうちに、サライスに余裕が無くなってくる。そして、とうとうサライスの長剣が弾き飛ばされた。
マイスはこの時点で勝利を確信した。が、そこに油断が生じた。
サライスは得物を失った事など意に介さずに、右手を地面に付くようにして体勢を低くするとマイスに対して足払いを仕掛けた。完全に油断していたマイスはこれをまともに受ける。
「な、何っ!?」
サライスは足払いの勢いを利用してその場で回転しつつ立ち上がると、その回転の力を流れるように放った回し蹴りに上乗せする。サライスの足払いによって完全に体勢を崩していたマイスにこれを回避する術はなかった。
「ぐぅ!」
体勢を崩した所に回し蹴りがまともに入ったために、マイスは完全に転倒してしまう。
マイスは即座に起き上がろうとするものの、その喉元に切先が突きつけられたために動きを止める。サライスの所持する短剣だ。
「はい、私の勝ち」
「な、に……?」
“決闘”というには、いささか卑怯な感じの勝ち方だが、別に騎士同士の決闘という訳でもないので気にするほどの事でもない。サライスもマイスも冒険者だ。常日頃「正々堂々」なんて事を考えながら戦ってなぞいない。最優先されるべきは「どうやったら勝つ事ができるか」「どうやったら生き残れるか」だ。
まぁ、本当にそれを最優先するなら、サライスの場合は最初から魔法を使っていれば、簡単に勝てていた。しかし、「“魔法”という常人には使用できない力は簡単に使うべきではない」と師に教え込まれている関係上、少なくとも命の危険の無い決闘の場で魔法を行使する訳にはいかないのだ。
「……うん、でも結構危なかったわ。これが実戦だったら魔法使ってるところよ」
「……は?」
「? どうかした?」
「……お前、魔法使えるのか?」
「あれ? 言ってなかったっけ? 私、魔法使い」
サライスは自身を指しながら(周囲の人たちにとっては)衝撃の事実を暴露。次いで「剣の方は、まぁついで?」などとほざいたものだから周囲の驚きはひとしおだ。
魔法使いでありながら、あれだけの剣の腕を持つ人間はそういるものではない。しかもそれを「ついで」などと言われたら、驚くのが当たり前だろう。
特にマイスの驚愕具合は見ていて不憫になるくらいだ。何せ、剣士であるマイスが魔法使いであるサライスに、サライスが魔法を使っていないにも関わらず敗れてしまったのだから。しかも、相手は見た目十五歳前後に見える少女。マイスの表情は今や“驚愕”と言うよりは“絶望”と表現した方が適切な域にある。
剣士としての腕前だけで見れば、マイスの方が数段上だ。ただ、今回はサライスの小細工が上手い具合に作用してしまったのが不幸だったとしかいえない。
「さて、前座も終わったし、人も揃ってるみたいだから、さっさと本題に入るとしようか」
最初に通された部屋に戻った際の高位神官殿の第一声だ。この男、一般的な高位神官に比べるとかなり若い、精々三十歳と言ったところだ。それが関係しているかは分からないが、聖職者にありがちな頭の固い印象は受けない。どちらとか言うと軽い印象を周囲に与える。
しかしながら、この年齢で高位神官をしているのだから、少なくとも実力面では優秀なのだろう。
今回の仕事の参加者はこの部屋にいる人間、総勢十三名で全てのようだ。その内、半数近くが冒険者で占められている。
(前座……)
サライスとしては、成り行きとは言え結果的には真面目に行った決闘を「前座」と言われるのは多少不愉快だ。が、まぁ文句を言うほどの事でもないので黙っておく。
もう一人の当事者であるところのマイスは、未だ意気消沈していて無反応だ。
「私は今回の件の責任者のレスター・ルイス。セラスターン教団で高位神官をしている。で――」
レスターが自分の隣、十七か十八くらいに見える少女に視線を向ける。
「今回の仕事の詳細の説明は彼女、リィス・タリスにしてもらう」
「セラスターン教団の修道士をしています。どうぞ、宜しくお願いします」
彼女はそう挨拶をすると、一歩進み出て説明を始める。
「まず、今回、アンデッドの浄化を行うに至った経緯から――」
彼女の口から語られたのは、アンデッドが発生した遺跡が発見されてから、その遺跡の調査隊の生き残りによりアンデッドの発生が発覚、冒険者ギルドに依頼するまでの詳細だった。
まず、遺跡が発見されたのが今年の緑の一月二十二日(2058-G1-22)、丁度一月ほど前の事だ。その後、調査隊の編成が決定され、実際に調査隊が遺跡に向かったのが今月の十一日(G2-11)、今日から数えて丁度十日前の事だった。
そして、今日から三日前、十八日になって調査隊の生き残りが重傷を負った状態で発見され、彼の口からアンデッドの発生が明らかになる。
これを受け、セラスターン教団は即座にアンデッドの討伐部隊の派遣を決定。その部隊の護衛を冒険者ギルドに依頼したのが昨日の夜の事である。
これが、リィスから語られた今回の経緯である。
因みにこの世界の暦は一年を四季により四分割しそれぞれを色で表す。その色はそれぞれ緑(春)、青(夏)、赤(秋)、白(冬)だ。そして、更に季節ごとに三分割しそれぞれ一月、二月、三月となる。そのため、緑の一月〜三月、青の一月〜三月、赤の一月〜三月、白の一月〜三月の合計十二ヶ月になる。一週間は六日、一月は五週で三十日、緑の一月一日が正月に当たる。なので一年は三百六十日という計算になる。
「さて、ここまでで質問はありますか? 無いようなら今回の仕事の詳細説明に移りますが」
そう言って、リィスは部屋の面々を見渡す。サライスも周囲の人間の様子を窺ってみるが、どうも質問しようという人間はいないようだ。仕方がないのでサライスは自分で質問する事にする。サライスは「質問ありますか?」と言われて何も質問しないのは、なんとなく気分悪く感じる人間なのである。そういうわけでサライスは軽く手を上げて口を開いた。
「いいかしら?」
「あ、はい。どうぞ」
部屋中の視線がサライスに集まる。そんなものが気になるほどサライスの神経は繊細ではないので、特に緊張するでもなく普通に質問を開始する。
「なんで冒険者に護衛を? 普通、セラスターン教団が動くのなら教団お抱えの聖騎士団が護衛に付くはずでしょ? この場にいる人間を見た限りじゃ、聖騎士はたった二人しかいないみたいだけど、どうなってるの?」
現在、部屋にいるのは教団の高位神官一名、リィスを始めとする修道士が四名、聖騎士二名、残りの六名が冒険者だ。
教団関係者や聖騎士は服装で丸分かりなので、この辺の認識に間違いがあるとは思えない。今回護衛に参加すると思われる聖騎士がたったの二名、それも明らかに“新人”という感じの二名だけである。これは明らかにおかしい。
そもそも、聖騎士団はその規模や戦闘能力では大陸トップクラスの武力集団だ。護衛に冒険者を雇った時点で中々異常である。
「それについては私が答えよう」
サライスの質問に真っ先に反応したのはレスターだ。
「結論から言えば、今現在、聖騎士団はこちらに人員を割く余裕がないからだな」
かなり大規模な組織である聖騎士団が他に割く人手がない。というのは不思議な話だ。
「……聖騎士団が人手不足になるような事態ってのが想像できないんだけど?」
考えられるのは戦争や大規模な自然災害などだ。これらが発生すれば聖騎士団が人手不足になる事も理解できる。が、そんな事が起こっていればギルドを通して情報が入ってくるはずだ。そうである以上、サライスには聖騎士団が人手不足になる要因が思いつかない。
「それについては話す事ができない」
要するに「聖騎士団は人手不足のため動けない」としか言えない、という事だ。少なくとも冒険者に対して『聖騎士団が人手不足になっている要因』を話す事はできない、という事は理解できる。
「そう、分かったわ」
「おや、あっさり引き下がったね」
サライスがあっさり納得したのが不思議だったのかレスターが声を上げる。
「別に、予想通りの返答だったもの」
「……うむ、予想通りなら、わざわざ質問する必要もなかったのでは?」
「必要あるわよ。たとえ返答が予想通りでも『私がこの質問をした』という事実は残るし、それが重要なんだから」
「なるほど」
レスターは納得の意を表す。確かに“質問した”という事実があるのとないのとでは、相手に与える印象が違うだろうから重要と言えなくもない。
それに予想通りの答えが返ってきたとしても、全くなんの情報も得られないという訳でもない。相手の反応で色々推測する事もできるだろうし、第一自分の予想に裏付けを付けられるというのは、かなり重要だと思われる。
今回の場合は、「話す事ができない」という返答が帰ってきたわけだが、これは『冒険者には話せないなんらかの事情がある』という事をレスターは暗に宣言してしまったようなものだ。やはり、サライスの質問は“無意味であった”とは言えないだろう。
「では、次に進みます」
サライスの質問に区切りが付いたのを確認し、リィスが話を進める。次の話題は『実際の仕事の詳細』である。
リィスは一枚の地図を部屋前面の壁に張り出し、その一点を指し示す。
「ここが現在地、クラベンスです。ここから――」
リィスは今指し示していた点に画鋲を一つ刺すと、地図上のクラベンスから北西方向に進んだ一点にもう一つ画鋲を刺し、その地点を指す。
「北西に進んだ――ここが目的地となる遺跡です。徒歩で約三日、ディスカット連峰に程近く森の中という事もあって、馬などによる移動は不可能です。片道三日の徒歩は必須ですので、それを考慮して装備を準備してください」
リィスは更に途中に休憩できるような町や村などもないという旨も伝えると、張り出した地図の横に更に紙を張り出す。
「そしてこちらが、調査隊の生き残りからの情報により作成した遺跡内部の見取り図です。地下遺跡ですので光源なども用意しておくと良いでしょう」
その見取り図によると、遺跡の入り口付近が大きな広間のようになっており、そこから三方向に向かって通路が広がっているようだ。
実際にアンデッドを浄化するための儀式を行うのは入り口付近の広間だ。ここで儀式を行えば遺跡内のアンデッドを一掃できるらしい。浄化の儀式を行うのが高位神官であるレスター・ルイス、儀式の補助にリィス・タリスを始めとする修道士四名がつく。
聖騎士二名と冒険者六名の役割は儀式が無事に終わるまでの間、敵を近づけさせない事である。
聖騎士二名はレスターやリィス達を直接護衛し、冒険者六名は三隊に分かれてそれぞれの通路をカバーする事となった。聖騎士が儀式の護衛に回されたのは、同じ教団のメンバーという事で連携も取りやすいだろうという配慮だ。聖騎士団もセラスターン教団には変わりない。
さて、そうなると冒険者連中の分け方が問題になるのだが、今回参加する冒険者はサライス以外皆パーティーを組んでいた。それぞれ二人組、三人組だ。本来ならパーティーごとに行動した方が連携の面で見ても効率的なのだが、そうなるとサライスが単独行動になってしまう。当然、それは危険だろうと皆が考えた。
「単独行動の方が良いんだけど。私、味方も攻撃しかねないし」
これが、サライスの意見である。聞いた人間からしたら「味方も攻撃しかねない」というのが意味不明だ。当然、その辺が問い質される。それに対するサライスの答えが以下である。
「や、私の得意な攻撃魔法って“敵も味方も関係なく、とにかく全部吹っ飛ばす系”だから。はっきり言って即席の連携って危険なのよ。主に味方が」
サライスが得意とする攻撃魔法は自身の魔力量にものを言わせた“力押し”である。剣による戦い方とは正反対だ。しかし、力で上回っているなら“力押し”というのは単純でいて有効な手段なので、そういう戦法になるのも当然なのかもしれない。
しかし、そうは言っても単独行動が危険な事には変わらない。しかし、誰かが一緒に行動すれば、“一緒に行動した人間が”危険なのだ。これだけ見るとサライス、かなり迷惑な人間である。
結局、サライスの――
「いや、今この場にいないけど、一応、相棒もいるから。本当、私と行動する必要ないから」
という発言により、冒険者の部隊分けは、二人パーティー、三人パーティー、それにサライスプラスこの場にいない相棒。という事になった。
サライスの言う“相棒”は、当然の事ながらグラストの事である。
その後、それぞれ簡単な自己紹介をすると、この日は解散となった。
「――大気中の魔力濃度が極端に低い空間内では魔法の発動が極端に難しくなる。実質、魔法は使用できないと考えて問題ない」
「え? どうしてですか?」
「例えるなら、水に塩を溶かすようなものだ。最初は簡単に水に溶ける塩も、ある程度以上溶けてしまうとそれ以上は溶かす事が出来なくなる。大気と魔力の関係もこれに似ている。すなわち、大気中の魔力濃度が極端に低い場合、魔法発動に使うはずの魔力が魔法発動前に大気中に溶け込んでしまい、まともに発動する事が難しくなる。また、この理屈で“魔法”と言うものを説明すると、『一時的に大気中の魔力濃度が飽和状態になり、それにより実体を持つに至った魔力の影響により引き起こされる現象』これが魔法だ。魔法発動のために『魔力を集中する』と言う動作が『大気中の魔力濃度を上昇させる』事と同等の意味を持つ訳だ」
「実体ですか」
「うむ、実際には『実体』とはちょっと違うんだが、魔力が周囲に物理的な影響を及ぼす状態になる事をここでは『実体』と表現している。これは、さっきの水と塩の例で言えば、水に溶け切らなかった塩の結晶に当たるな。ここで重要なのは、最初に言った『魔力濃度が極端に低い空間』、こんなものは自然にはまず発生しない、というところだ」
「え? じゃあ、別に知らなくても良いんじゃないですか?」
「馬鹿者。『自然に発生しない』と言う事は実際にこの空間が発生した場合、これは『人工的に生み出されたもの』である可能性が極めて高いと言う事だぞ? なんらかの罠である可能性も高いだろう。何せ魔法使いを無力化する効果的な方法の一つだからな。実際、世の中の防御魔法の中にはこの理屈を応用したものも少数ではあるが存在する。……魔法に対してしか効果を発揮しないからあまり使われないけどな」
早朝、日の光と鳥のさえずりによってサライスは目を覚まし、ベッドの上に起き上がった。
「……なんとも懐かしい夢を」
サライスが見た夢は魔法の修行を始めた初期の頃(とはいえ、修行を始めてから二〜三年は経過していたが)の出来事だ。当時十歳であったサライスはあまり理解していなかったのだが、今では当然のように知っている事である。
現在の魔法は、魔法使い本人の魔力によって発現するものだ。大気中から魔力を掻き集めて魔法に利用する訳ではない。そのため、基本的には大気中の魔力濃度というものを意識する事はない。が、大気中の魔力濃度というものが魔法に与える影響は本来無視できるレベルのものではないのだ。特に魔力濃度の極端に低い空間、俗に『魔力枯渇空間』と呼ばれる空間は魔法使いにとってまさに天敵と呼べる存在だ。
だからこそ、サライスの師匠はサライスに魔法だけでなく、剣術も教えたのだ。おかげでサライスは『魔法が使えないから何もできない』という情けない状態に陥る事がない。普段、魔法を極力使わないのも、魔法に頼らない行動に慣れておくという意味合いもあるのだ。
また、魔力枯渇空間の対極の存在として『魔力飽和空間』というものもある。こちらは逆に極端に魔法が『発動しやすい』。それだけなら魔法使いにとって有利な空間のように思えるが、これはこれで色々問題がある。魔法使いが意図しないタイミングで魔法が発動したり、簡単に魔力が暴走したり、とまぁ魔法使いにとってあまり良い事はない。魔法が発動しやすいというのは、確かに魔法使いにとって良い事と言えるが、何事にも限度というものは必要だ。そういう意味で魔力飽和空間内での『魔法が発動しやすい状態』は、その限度を遥かに超越している。例えるなら、可燃性ガスが充満した空間内で火を扱うようなものである。が、こちらの方は魔力制御に優れた魔法使いならなんとかできるので、魔力枯渇空間に比べればいくらかマシだ(あくまで『魔法の領域で対処が可能である』という意味合いで、だが)。
「さて、準備しますか」
準備といっても、既に荷物などは用意してあるので、殆ど着替えるだけで準備完了だ。
そのため、それほど時間もかからずに準備を終えると、さっさと集合場所に向かった。
サライスは目が覚めてから、特に時間を確認するでもなく集合場所に向かったためか目的地に到着したのは集合時間の三十分近くも前だった。
それでも、既にその場所に待機している人間がいたのだから、サライスとしても多少は驚く。
「あ、おはようございます。お早いですね」
「いや、貴方に言われたかないけど」
サライスに挨拶してきた青年、名をキラテス・ダースという。護衛に参加する聖騎士の一人で今回が初任務らしい。
因みに今この場にはいないが、昨日もう一人いた聖騎士はカイ・マスイットといって、同じく新人ではあるらしいが今回が初任務という訳ではないらしく、キラテスからしたら先輩に当たるらしい。
現状、サライスとキラテスの二人しか集まっていないので、必然的に二人で会話する事になる。とは言え、昨日出会ったばかりではそれほど話題は多くない。
「相方はまだ来てないの?」
「相方……? ああ、カイ先輩ですか?」
「それ」
「多分、ギリギリに来ると思いますよ。いつもそうですから、遅刻はしないんですけどね」
キラテスが苦笑気味にそう言う。サライスはそれに対し「ふーん」と気の無い返事を返す。初対面に近い人間同士の会話なぞこんなものだ。
それからしばらくお互いに沈黙したまま時が進む。時間にして数分ほど経過したとき、今度はキラテスから話しかけてきた。
「……サライスさんは魔法使いなんですよね?」
「ええそう。……それが?」
キラテスに視線を向ける。「それがどうした」と読み取れる表情だ。
「ああ、いや。ただ、どうして剣と使っているのかと……」
「……魔法使いが剣を使うのは、駄目だと?」
「いやいや、そうではなくて、珍しく思ったので聞いてみただけで」
「ふーん」
“魔法使いが剣を使うのは珍しい”というのは、まぁ常識的な見解だろう。
「先生が言うには」
「先生?」
「私に魔法と剣を教えてくれた、師匠よ」
サライスからしてみると、自身の師匠も魔法と剣を使う所為か、珍しいとは思えない。……ただ、“あの先生”を基準にしてはいけないという事も理解はしている。理解はしているが何せ、魔法にしても剣にしても、サライスにとって最も身近に感じるのが師である。無意識のうちに基準にしていても仕方が無いだろう。
「その先生に言わせると、私には『攻撃性の魔法を使った近接戦闘』は向かないらしいわ。特に『お前は屋内とかの閉鎖空間内での近接戦闘で攻撃性の魔法を使うと、自爆しかねん』とまで言われたらね。流石に使う気にならないでしょ? で、その代わりの剣、どうも剣の方はそれなりに向いてたみたいだし」
「なるほど」
サライスの師匠の教育方針は『長所を伸ばし、短所は放置』である。弟子に向いていない方面の技術は必要最低限にしか教えないのである。
おかげで、サライスは得手不得手がはっきりしている。因みに、サライスは長剣や短剣などの『片手で扱うことが前提となっている刀剣類』の扱いは教えられたが、徒手状態における戦闘技術は決闘で見せた足払いや回し蹴りなどの、剣を持ちながらもある程度使える“足技”以外は教えられていない、「それは向いてない」という事なのだろう。
会話に一区切りがつくと二人はまた沈黙した。こんな感じでサライスとキラテスが会話と沈黙を繰り返すうちに集合時間になった。
結局、キラテスが言ったように、カイがギリギリにやって来たのが最後で遅刻者はいなかった。まぁ、今回のような仕事で遅刻するような奴は中々いないだろう。
メンバーが集まった時点で直ぐに出発した。現在は主要都市間を結ぶ大きな街道から遺跡に向かうために、わき道に逸れた辺りである。ここから二時間も歩けば、そこはもう“道なき道”と言っても良い状態になるそうだ。
さて、現状でグラストはまだ合流していない。そうなると、周りは“サライスの相棒”がいない事を疑問に思うものだ。出発前に質問された時には「途中で合流する」というサライスの言葉に納得したものの、ここまで来ると多少なりとも不安になる。
「サライス君、君の相棒はいつ合流するんだい?」
「ん? ……まぁ、そろそろ良い感じだけど」
レスターの言葉にサライスはさっと周囲を見回すと考える。
とにかく、グラストは人目のある場所では出てこない。ただ、仕事仲間の前にまで出てこないという事は流石に無く、一般人の目が無くなれば自然と出てくるはずである。
そういう意味では街道から逸れた現状では、いつ出てきてもおかしくは無い。
そう思いサライスは周囲の気配を探る。サライスとグラストは互いの位置が大体分かる。というのも、グラストはサライスの魔力を糧として生きているため、お互いの間にある種の“繋がり”があるのだ。
「ん、いた。もう出てくるわよ」
グラストの位置を確認したサライスはレスターに対してそう返した。その時であった。
「うわっ!?」
進行方向に向かって前方から声が上がった。
現在の配置は最前列に三人パーティーの冒険者。最後尾に二人パーティーの冒険者。その間に高位神官及び修道士、そしてその付近で彼らの護衛をするのが聖騎士とサライス、というものだ。
「お、狼だっ!」
何やら、皆、戦闘態勢になっている。そんな中、サライスがのんびり声を上げた。
「あー、あー、それ、私の相棒」
「はぁ? そんなわけあるかっ!」
代表して突っ込みを入れたのはマイスである。一晩たって流石に復活したらしい。
先頭三人の冒険者は、こんな中でも戦闘態勢を解いていない。まぁ、様子見の状態になってはいるが、サライスの言葉一つで油断するほど彼らも弱くは無い。
サライスはそんな彼らを無視して、グラストの前まで進むと軽く挨拶する。
「やっほー、グラスト」
【お嬢、仕事を取ってくるのは良いが、事前に説明くらいしておけ】
「や、言葉で説明するより、実際に顔合わせたほうが早いっしょ?」
サライスはグラストにそう言うと、後ろを振り返る。
「という事で、これが私の相棒で、グラスト。グラスト、自己紹介」
【お嬢……、我の言葉が理解できる人間がこの中にいるのか?】
「え? ああ、そっか。普通の人は分からないんだった」
サライスは改めて“仕事仲間達”に言葉を投げかけた。
「このグラストは仲間なんで、どうぞよろしく」
第三話 【不死の魔物 III - 成功の定義】 目次
さて、時間を遺跡内でのアンデッド討伐時に戻す。
大規模な凍結魔法で敵を根こそぎ氷付けにしたサライスは、アンデッドを浄化するための儀式を行っている本隊と合流するために走っていた。
サライスがあっさり持ち場を離れているのには理由がある。一つは、アンデッドスライムの存在、不測の事態が発生したのだから、それを本隊に報告に向かうのは当然だろう。
そして、もう一つはサライスが使った凍結魔法の存在である。あれは、一定領域内を完全に凍結する。――――だけでなく、一旦凍結した領域内に外から侵入した存在、これすらも凍結するのである。サライスはこの効果を長時間持続するために、魔法発動時に必要以上に魔力を注ぎ込んだのだ。本隊のいる入り口広間から、あの場所までは広間の地点で三方向に分かれている以外は一本道。魔法の効果が持続している限り、この方向からの敵の接近はありえない。
……サライスが感じた魔法行使時の感触では、一週間くらいは効果の持続が見込めるだろう。はっきり言ってやりすぎだ。こんなんだから、長剣が折れたりするのだ。
そうこうするうちに、入り口付近にある広間状の空間が近づいてきた。元々、サライスが戦っていた地点からそう離れた場所ではなかったので時間はかからなかった。
サライスは直ぐに儀式の準備を行っているレスターに近づくと、アンデッドスライムに遭遇した旨を伝えた。
「アンデッドスライム!? それはまずい」
アンデッド系の魔物と戦う機会が比較的多い、神官などの聖職者にとってはアンデッドスライムというのは一種の天敵だ。実際、アンデッドの浄化に赴いた神官が現場に行ってみれば、そこにいたのはアンデッドスライムでその神官は命を落としたという話も聞くくらいだ。
「では、儀式を終えたら、できる限り早く撤退します」
元々、アンデッドとの戦闘を想定して装備を整えていたため、その他の魔物――――特にアンデッドスライムなんていう変り種と戦うには装備が不足している。レスターの決断は極真っ当なものだ。
「そういえば、サライス君、剣は?」
レスターがサライスが短剣を持っている事と、腰に下げているはずの長剣が鞘ごと消えている事に気づいて尋ねる。
「え? ああ、折れた」
「折れた?」
「うん、魔法の基点に使ったらあっさりと」
「魔法の基点って……、なんの加工もしていない普通の剣を?」
【お嬢、呆れられているぞ】
「うっさい。――――良いじゃない、おかげであっち方面からの敵の接近は無くなったんだから」
会話の途中に割って入ったグラストの言葉に憮然と返す。その後半の言葉にレスターが反応した。
「敵の接近が無いとは?」
「ん、全部氷付けにして来たから、一週間くらいはずっと氷付けじゃない?」
サライスの言葉に、レスターの表情が若干引きつるが、それを気取られる前に元の表情に戻す。流石に高位神官をやっているだけあって、感情を隠すのが上手い。
「それは、少しやりすぎでは?」
「え、……そう?」
【だから、言っただろう。『出力上げすぎだ』と】
「むぅ」
「まぁ、そういう事なら貴女方は、マイス・メイラ組の応援に向かってください。あのパーティーは魔法使いがいないので、アンデッドスライムがいるとなると少し心配です」
今回参加した冒険者六名の中で、魔法使いは二人、一人はサライス。もう一人はスクライル・ドーランドといって三人組の中の一人だ。
スライム系の魔物との戦闘は魔法使いがいないと、いささか厳しいものがある。そのため、魔法使いがいない組に応援。という考えに至るわけだ。
サライスもそう言われる事を予測していたのか、あっさり肯く。
「分かったわ。グラスト、行くわよ!」
【うむ】
そういうと、サライスが走り去る。それを横目にレスターは近くにいた聖騎士の青年に声をかける。
「カイ君、ここは良いですので、三人組の方に伝言をお願いします。『儀式終了後、即時撤退』と、それとアンデッドスライムに気づいていないようだったら、その事も伝えておいて下さい」
「わっかりましたっ!」
カイは威勢良く返事をすると、すぐさま走り出す。
そのカイが走り出したのとほぼ同時に修道士の一人がレスターに声をかけた。
「レスター様。儀式の準備、整いました」
「良し、それでは、これより浄化の儀式を執り行う!」
こうして、今回の仕事の最重要事項。『浄化の儀式』が始まった。
サライスが現在応援に向かっている、マイス・メイラ組は先日サライスと決闘をしたマイス・カライスと、そのパートナーであるメイラ・シルウェイのパーティーである。
マイスは今更確認するまでも無く、長剣を扱う剣士で、対するメイラは短槍使いである。どう考えてもアンデッドスライムに対抗できる戦力ではない。故に早急に合流する必要があるのだ。
こうして彼らの元に急いでいる時、甲高い“音”が響いた。その音は遺跡の壁に反響してどの方向から聞こえたか判然としなかったが、その正体だけは歴然としていた。
「グラスト! 先に行きなさい!」
【承知だ!】
――――それは、人の悲鳴。そして、性別は恐らく女。
それをサライスは理解すると同時にグラストに対して指示を出していた。
グラストは狼をベースとする魔法生命体だ。人間でしかないサライスを遥かにしのぐスピードで走る事ができる。そのため、グラストを先行させた方が相手の助けになる。
反響のおかげでその悲鳴の出所は分からないが、性別が女であるなら可能性は限られる。今回の部隊、十三名の中に女性は四名。さっきの悲鳴の正体から真っ先に除外されるのは、当然の事だがサライス。残りの三人の内二人は修道士であるリィスとメリッサ・カアスラだ。彼女らはレスターの元で儀式の補助を行っている。仮に先ほどの悲鳴が彼女らのものだったとしても、あそこには仲間がそれなりにいるし、そもそも神官や修道士はある程度は魔法が使えるはずだ。そうである以上、ある程度の対処は可能だと判断できる。
そして、残りはサライスが向かっている先にいるはずのメイラだ。はっきり言って最も可能性が高いのが彼女である。マイスとメイラの組だけその場に魔法使いがいない。アンデッドスライムの存在を考慮すると、他の魔法使いのいる場所より危険度は遥かに高い。
一定の間隔で落ちている照明石の明かりを頼りに走っていたサライスの目に、倒れている人影を二十体ほどのゾンビから守るように立ちはだかるグラストが映る。
「グラスト!」
【お嬢か】
近づくと倒れているのはメイラである事が分かる。パッと見ただけでも明らかに意識は無い、そして十分な明かりが無い所為で傷の程度は分からないが一目で命の危険があると思えるだけの出血も見られる。サライスはグラストの横に並びながら口を開く。
「助かりそう?」
【無理だ。今から応急処置をした所で、気休めにもならん】
「っ……」
グラストの即答にサライスの表情が一瞬消える。だが、今この場で感情的になる訳にはいかない。
「そう。……彼女、誰にやられたのかしら」
それは単純な疑問だった。今回の仕事に参加しているメンバーにはゾンビ程度の魔物に簡単に倒される人間はいない。
【お嬢。答えの出ている質問をするな】
「そう……ね」
サライスは視線を前方の人影に向けた。
――――その人影は右手に長剣を持った。
――――恐らくはアンデッドスライムに肉体を乗っ取られた。
――――マイス・カライスだった。
この事態はアンデッドスライムの存在を確認した時点で想定できていた。しかし、実際にこういう事態になってしまうまで、その考えは意識的に避けていた。考えても仕方ないからだ。
しかし、こうなってしまったからには対処せざるを得ない。例え元々が仲間だったとしても、今は敵だ。戦わなければならない。
【お嬢、できるか?】
「大丈夫。人を殺して経験くらいは私にだってあるんだから、そんなに心配しなくても平気よ」
【……殺す必要は無いだろう。儀式が終わるまで時間を稼いでおけば良いのだろう?】
「……分かった」
そう言うと、サライスは時間を稼ぐように動き始める。グラストはいつでもサライスのサポートに入れるように立ち回る。今のサライスはグラストから見て、若干不安に感じるのだ。
サライスがグラストの言葉を曲解する事は滅多に無い。それだけ、この状況がサライスの精神に与えているダメージが大きいという事だろう。
今回の仕事のメンバーの中では、マイスとはお互いに剣を合わせただけに比較的親しいと言って差し支えないだろう。どちらかと言うと“喧嘩友達”と言った感じだったが……。その関係で、マイスのパートナーであるメイラともそれなりに話をする間柄になっていた。
集団の中で比較的親しく付き合っていた人間二人が、一方は死に、もう一方は魔物の操り人形状態だ。この状況下で、平静を保つのは難しいものがある。内心での精神状態はどうあれ、激しく取り乱したりしないだけ、サライスは褒められても良いくらいだろう。
しかし、それでも心を乱している状態では動きに若干の違和感が出てくるものだ。そういう意味で現在のサライスは普段からは考えられないミスをする可能性もあるため、目を離せない。
そのサライスは、殆んど体捌きだけで動きの鈍いゾンビらを牽制しつつ、口を開く。
「ねぇ、グラスト。これ、自然発生だと思う?」
【……これだけの数のアンデッドが自然発生するとは思えないな。その上、アンデッドスライムまでいるとなると】
「そうよね、やっぱり黒幕がいるわよね」
ここまでくると、グラストもサライスが言いたい事が理解できる。それくらいの予測ができるくらいには付き合いが長い。
【お嬢、今我らがやるべき事は、真相の究明でも、黒幕の断罪でもないぞ。それに、この場に黒幕がいるかも分からないんだ。早まった事はするべきではない】
サライスはグラストの言葉に返事を返さずに、近場の人影を一つ蹴倒すと数歩後退し口を開いた。
「グラスト、一発大きいの使うから援護して」
【お嬢!】
グラストはサライスをたしなめるように呼ぶ。
時間稼ぎに徹するならば大きな攻撃なんて必要ない。先ほどはアンデッドスライムの出現という不測の事態を本隊に報告しなければならなかったため、大きな魔法を使ったのだ。今回は本当に時間を稼げば良いだけだ。積極的に攻勢に出る必要は全くない。
「分かってる! 分かってるわよっ! 今自分がやるべき事くらいっ! でも、……でも、ちょっと暴れさせてっ……!」
【……了解だ】
今のサライスにとって、“暴れる”というのは自らの気持ちを落ち着かせるために必要な行動なのだろう。グラストにもその気持ちは分からなくも無いので、サライスの言葉に了解する。これでもし、サライスが何らかのミスをするなら、その時はグラストが全力でサポートすれば良いだけの話だ。
(……元々、我はそのために存在するのだからな)
グラストは、サライスを絶対に死なせない。それはグラストの存在理由でもあり、サライスの師であり自らの生みの親でもある“大いなる魔法使い”との契約でもあり、そして、自らに課した誓いでもある。
グラストはサライスより後に死ぬことは無い。それはグラストの絶対の決意だ。それこそ、十年前、この世に生み出された時からの……。
「グラスト。直射反射追尾弾、分裂バリエイションで行くわよ」
【それはまた、マイナーどころを】
「今は全力を出したいから、これなら大量の魔力を使っても他の攻撃魔法に比べて威力が出ないから、ここに生き埋めって事にもならないだろうし、……その割りに派手だし、丁度良いわ」
『直射反射追尾弾』、これの基本形は単純な直射系射撃魔法だ。ただ、一直線に魔力弾を放つ魔法。これにある機能を付加したもの、それが『直射反射追尾弾』だ。その機能というのが『ターゲットを外した場合、その先にある障害物を反射して、ターゲットを追尾する』というものだ。通常の追尾弾が曲線を描くようにしてターゲットを追うのに対して、こちらはあくまで直線的にターゲットを追う。そのため、通常の追尾弾に比べて弾速が早いのが特徴だ。ただ、反射する障害物がないとターゲットを追尾する事ができないという欠点も抱えている。現在地である地下遺跡はこのタイプの魔法を使うのに最適だといえる。
そして、この魔法の分裂バリエイション。これは、魔力弾がターゲットに命中した時、及び障害物により反射した時に『分裂する』というものだ。分裂した魔力弾はそれぞれ別のターゲットを追尾する。
使い所さえ間違わなければ、かなり有効な魔法だといえる。だが、実戦で使う人間はまずいない。
実戦で使用される攻撃魔法に要求されるものは、“技術レベルが低い” “消費魔力が低い” “それでいて威力が大きい”である。すなわち『楽で、燃費が良く、高威力』である。
『直射反射追尾弾、分裂バリエイション』は、このどれにも当てはまらない。技術レベルは高いし、消費魔力は大きいし、消費魔力が大きい割りに威力は低い。すなわち『難しく、燃費が悪く、低威力』、……最悪である。
だが、だからこそ、サライスのように保有魔力量が馬鹿のようにある魔法使いが、全力で使用しても“この遺跡が崩壊しない”のだ。
「グラスト! 行くわよ」
【了解だ!】
手始めにグラストが近場にいた一体の敵を体当たりで突き飛ばす。サライスは十分な距離を後退すると左手のクリスタルをしっかり握り締め、正面を睨む。
視線の先は、マイスだ。アンデッドスライムに寄生された以上、サライスに彼を助ける手段は無い。できるとしたら一つだけ。
(私が、殺す)
一時的にとはいえ、仲間であった者の責任として、サライスは彼を殺す。最早、彼を助けることはできない、だからこそ、彼の肉体を魔物の操り人形のままにしておく事はできない。――――させない。
アンデッドスライムは生きた肉体に寄生する。だから、肉体的に殺せば、アンデッドスライムの呪縛から解放する事ができる。
サライスはもう一度、左手をしっかり握り締めると、呪文の詠唱を開始した。
「ラナトゥル・ィエトルナ・ハルマー・カラ・ラネスティル・ラタ・クリータル・リフカル・バッシュ!」
呪文の詠唱と共に、サライスを中心として光の粒子が渦を巻く。それは視認が可能な域まで高密度化された魔力だ。通常の魔法使いでは考えられない程の膨大な魔力が、サライスの感情を表すかのように荒々しく渦を巻く。
サライスはクリスタルを握った左手を頭上に突き上げ、呪文の詠唱を続ける。
「光り輝く魔力の奔流よ! その姿が砕け散ろうとも、その最後の輝きが尽きるまで、普く全ての敵を追え! 追え! 追え! 追え! 敵を討ち滅ぼすまで追い縋れぇ!」
サライスの頭上、突き上げられた左手拳のさらに数メートル上。その一点に周囲を渦巻いていた膨大な魔力が収束する。
そして、直径二メートルになろうかという、巨大な、魔力の塊が、遺跡内を煌々と照らしながら浮かび上がった。
これがサライスの力。通常の魔法使いをはるかに凌ぐ魔力量にものをいわせた“力押し”の魔法。この魔法はその性質上、威力が低い。それでも、これだけの魔力が集まれば、人の十人は軽く殺せる。もっと効率の良い攻撃魔法に、これだけの魔力を使えば数百人規模の集落を一瞬で抹消できる。それだけの魔力。
「行けぇーーーー!」
絶叫にも聞こえる号令、それと共にサライスは左手を振り下ろす。それに合わせて、巨大な魔力弾が高速で動き出す。
向かう先は一直線。マイスの肉体を破壊せんと突き進む。
――――――サライスは、この日初めて、“仲間だった人間”を殺した。
これは、クラベンスから件の遺跡に向かう途中の話。
グラストと合流してから一晩が経過した日の昼。以前、遺跡の調査隊が通ったルートとはいえ、道と呼べるほどのものが無い森の中を進むのは、かなり体力を消耗する行為である。しかも、遺跡はディスカット連峰に近いと言うのだから、これから傾斜も厳しくなる可能性が高い。楽な道程とはお世辞にも言えない。
必然的にこまめに休憩は入れるし、日が落ちれば野営も張る。今も、そんな休憩のうちの一回だ。
サライスは一人、他のメンバーから離れて小川近くに座っていた。その近くにはグラストの寝そべっている姿も見える。
そんな“二人”に近づく女性の姿があった。彼女はメイラ・シルウェイ、サライスと決闘を行ったマイスのパートナーである。年齢もマイスと同年代、二十代後半だ。
その接近に最初に気がついたのはグラストだった。グラストはメイラの存在を察知し顔を上げた。そのグラストの動作でサライスもメイラの存在に気がつく。
ほぼ同時に二対の視線にさらされたメイラは一瞬、その歩みを止めるがすぐにサライスの方へと近づいていく。
「何か用が?」
先に口を開いたのはサライスだ。
「用、というか、少し話したいなと思ってね」
そのメイラの返答にサライスは一つ頷く。それをメイラは了承と受け取って、サライスの隣に腰を下ろした。その際、グラストに一瞬視線をやると、グラストの視線はすでにメイラにはなく、興味無さ気に寝そべっていた。
次にメイラが気づいたのは、サライスの足元。
「……リス?」
サライスの足元に存在する小動物。その名をメイラは口にする。
そのリスが鳴き声を上げると、それにサライスが反応を示した。
「そう? またね」
リスはそのサライスの言葉とその顔に浮かべた微笑を受けて(少なくともメイラにはそう見えた)、この場を去った。
その様子を見ていたメイラが口を開く。
「えっと、今のは?」
「友達、少し話をしてたのよ」
「動物と話せるの?」
「ええ」
サライスはメイラの質問に即答する。動物と意思の疎通ができるのは昔からの事だ。今更、返答を躊躇う類のものでもない。
サライスの動物と会話する能力は、昔から、それこそ生まれた時から持っていた能力だ。普通の人間に“言葉を話すための機能”が付いているのと同じように、サライスは“動物と会話”ができた。
この能力は魔法ではない。その事は、サライスの師匠によって証明されている。が、では「この能力はなんなのか?」と問われても答えられやしない。分からんのである。
だが、この能力の正体が分からないからと言って、サライスに問題がある訳でもないので、殊更それを追求しようとはサライス自身思ってはいない。多分、一生“正体不明の能力”という事になるのだろう。
メイラに質問されるままに、サライスはその辺りの事も話して見せた。サライスにとってこれは人間が持っている“個性”と同レベルの話題である。隠す理由が無い。
「へぇ、なるほど。その力って便利?」
「便利……というか、私にとってこれが普通だから、便利とか不便とか、そういう判断はしにくいわね」
サライスはそう答えた後、「…でも、困る事も多少はあるわね」と続ける。それを聞いてメイラが先を促す。
「……食事、がね」
「食事?」
「動物の肉が食べられないのよ。私」
「え、そうなの?」
「……意思の疎通ができる相手を“食材”として見れる?」
「……ちょっと無理かも」
メイラは想像して、顔をしかめた。メイラにとって“意思の疎通ができる相手”となると基本的に“人間”だ。それを“食材”としてみる。普通の神経をしていれば無理である。
「そういう事、私にとっては動物も人間も変わらないし。……魚は食べれるけど」
サライスの能力でも、流石に“魚類”と会話する事はできない。おかげで、とりあえず魚は食べられる。
実際問題、“肉が食べられない”というのはかなり不便だ。料理屋で食事を注文すれば、普通に肉なんて入っているものだし、冒険者が携帯する食料だって、干し肉が中心だ。
実際、サライスが旅をする時、最も問題となるのが、この食料調達なのである。能力によって引き起こされた問題の中では、これが一番重大だろう。
それを聞いたメイラは「あっ」と何かに気づいたように声を上げる。
「だから、食事の時とか、一人だけ離れてるの?」
それは図星である。自分と会話が可能な存在が食べられる姿を見て、平気でいられるほどサライスは人間を捨ててはいない。
「……正解」
これが、サライスとメイラが初めてまともに会話した時の事だ。その後、彼女らはしばしば会話するようになる。本人たちがどう思っていたかはともかく、周囲から見れば彼女らの様子は、出会ってからの期間を考えれば“親しい友人”と言っても問題ないものであった。
結果だけを言えば、依頼は成功だった。依頼内容はあくまで浄化部隊、この場合は神官や修道士の護衛であって、それらの人物に死傷者はいなかった。冒険者が幾人か死んでいたとしても彼らが無事なら依頼は成功であり、報酬も出る。
“仲間の死”それは依頼が成功した云々とは関係なく、気分の沈む出来事である事に変わりはない。たとえ、今回の仕事の危険度から、それなりに高額の“追加報酬”が約束されたからといって、簡単に気分が上向くものでもない。
その“追加報酬”にしたって、“冒険者が二人も死んだ”という事実があったがために膨れ上がったようなものだ。素直に喜んでなぞいられない。
その死んだ仲間の一人を“物理的に殺した”サライスからすれば、尚更、喜ぶ事なんてできはしない。
あの遺跡から脱出したその日の晩。サライスは森の木々の間から見える星空を、一人見上げていた。
【お嬢】
「ん、どうしたの?」
サライスはグラストの方を見もせずに返事をする。十年間ですっかり聞きなれた声と気配だ。視界に入らずとも、グラストである事はすぐ分かる。
【大丈夫か?】
「……大丈夫、って言ったら信用する?」
【しない】
「だったら聞かないでよ」
サライスが不満気な表情をグラストに向ける。
【……一人にした方が良いか?】
「……そうね。そうしてもらえると助かるかも。……明日までには調子を戻すから」
【別に、しばらく落ち込んでいたって構わんが?】
「私が構う」
【そうか?】
「そうよ」
グラストは、しばらくサライスに注視すると、納得したように頷きサライスの元から去った。
グラストは魔力の供給さえあれば、基本的に食事や睡眠を必要としない。夜の間はどこかで暇を潰すのだろう。
サライスはグラストを見送ると視線を夜空に戻した。
「まったく、私はそんなに弱くないっての」
その言葉には、どこか自分に言い聞かせるような響きがあった。
第四話 【パーティキュラー・マター】 目次
ごめんなさい。初めて貴女を見た時、てっきり年下だと思いました。……まさか、二十歳だとは……。
「リィス君。ちょっと」
それは、あの遺跡から帰ってきた日。……の翌日。ついでにその午前中。
私は教団の高位神官であり、私の師匠的人物であるレスター・ルイス様に、手招きと共に声をかけられた。
「あ、はい、なんですか? レスター様」
「うん、特に用はないよ」
…………。
「あ、いや、冗談だから。その笑顔やめて、なんか怖い」
……十七歳の女性にむかって“笑顔が怖い”って、……ひどいと思うんですが。
そりゃあ、ちょっとムカッときましたが……。
レスター様は何やら気まずげに視線をそらすと、一つ咳払いをした。さっきから態度が非常に失礼な気がするのですが……。
私は一つ溜息を吐くと、“我が親愛なるお師匠様”に声をかけた。
「それで? なんの御用でしょうか、レスター様」
満面の笑顔でそう言った私を見て、レスター様は冷や汗を流しつつ「怖っ」と小さく呟くという、とても失礼な反応と共に口を開いた。
「人を呼んできて欲しいんだ」
「人、ですか?」
「そう、“サライス・レイスト”っていう冒険者」
「はぁ、サライ――」
――って!
「あの、レスター様?」
「ん?」
「それって、護衛についてくれていた……?」
「うん、同一人物」
…………。
「えっと、良く分からないんですけど……、“冒険者”ではなく“サライスさん”を名指しで呼んで来い。という事ですよね?」
「その通り」
「はぁ、まぁ、それは分かりましたけど、もう街にいないかもしれませんよ?」
何せ相手は冒険者なのだから、既に旅立っていてもおかしくないと思う。
「ああ、それなら大丈夫だ。少なくとも今日は休息に当てると言っていたからね」
「あの、そんな事を聞いておくくらいなら最初から呼んでおけば良かったのでは?」
「忘れてた」
「……そ、ですか」
私はちょっと呆れながら呟いた。が、レスター様のとぼけたところは、いつもの事でもあるので気を取り直して口を開く。
「まぁ、分かりました。今すぐ呼んで来た方が良いですか?」
「ああ、そうしてくれると助かる」
「では、しばらく外出します」
「頼む」
私はレスター様との会話を切り上げると、サライスさんを探しに出かけた。
……とりあえず、冒険者ギルドで所在を尋ねよう。
その頃、サライスは武器屋にいた。今回の仕事中に盛大に折ってしまった長剣の代わりを調達するためだ。
サライスはギルドで武器屋を幾つか紹介してもらうと、実に「てきとー」に近場の店にやってきた。この辺、サライスにこだわりは無い。
店に入ったサライスは、そこの店員と“いつものやり取り”(外見が十五歳程度なので、中々武器を売って貰えなかったりする)をこなし剣を幾つか見せてもらっていた。
サライスの注文は――
「切れ味は二の次、とにかく頑丈さが第一。で、片手で扱える剣。予算は十万」
――である。
この世界、この時代の剣術の基本は「剣の自重と筋力でもって叩き斬る」か「剣で叩いて相手が怯んだ所を突く」である。そのため、剣自体も刀身に反りのない直刀がメインだ(対して曲刀は摩擦力を上乗せして“斬る”剣)。基本的に剣に刃物としての切れ味というものは求められていない。
その上で、サライスは「切れ味は二の次」と宣言している。これは要するに「ただでさえ、大して切れ味の良くない剣の中でも更に切れ味が低くても構わない」という事だ。もう、なんというか“金属の棒”が出されてもおかしくない勢いの言葉である。
そんなサライスが見ていた剣の中から一本、気になるものを見つけた。
(……これは)
それは剣士としてではなく、魔法使いとして気になるものだった。
サライスは、その剣を鞘から抜き良く見てみる。片手剣としては若干長く、重い刀身。片刃で反りの無い直刀。その刃に切れ味は殆ど無いと言っていい。だからといって、装飾が美麗な訳でもなく、観賞用という訳でもなさそうだ。
――形だけ剣を模した金属の塊。それが、多くに人間に与える印象だろう。
しかし、魔法使いとしての視点から見た場合、その印象はガラリと変わる。『魔法具』、これは明らかにそれに分類せねばならないものだ。ただの武器屋に置かれているのは不自然だし、予算十万で買えるような代物ではない。
恐らく、店側も気づいてはいないのだろう。武器の形をとる魔法具はただでさえ珍しいものだし、魔法使いでない人間にはそれを見分ける手段は基本的に無い。そして、普通の魔法使いは武器屋に用は無い。誰もこの剣の価値に気づかなかったのは、ある意味では当然だったのかもしれない。
しかし、サライスは気づいた。この剣に使われている素材、これは恐らく――
(……やっぱり)
サライスの疑惑は確信に変わる。少量の魔力をその刀身に流し込んで確認した結果だ。
恐ろしく魔力の伝導効率が高い素材がその刀身に使われている。サライスの膨大な魔力を一気に流し込んだところで損傷の恐れは皆無だろう。
具体的な素材の名称まではサライスには分からないが、それでもその価値は見て取れる。
ふと、剣の刀身に文字が彫られている事にサライスが気づく。
(……リ、ジェ……ダル?)
その文字は今では誰も使わない古典魔法で用いられていた文字だ。古典魔法は現在の魔法体系の基礎となっているので、それに関する知識もある程度サライスは師匠から与えられた。
その知識が彫られた文字を「リジェダル」と読み解いた。剣自体の名前か作者の名前か、恐らくその辺りだろう。
「これ、いくら?」
「ん、そいつは七万五千」
それを聞いたサライスは内心驚愕したが、表面上は平静を保った。下手に騒いで相手に物の価値に気づかれ、値を吊り上げられては困る。
しかし――
(私だったら、その百倍以上で売るわね)
サライスとしては、できれば剣の出自も聞いておきたいところだが、あまり突っ込んで尋ねて不審がられるのも困る。ここは自粛すべきだ。
極力いつも通り行動する事にする。
「……五万」
「おいおい、そりゃいくらなんでも無いだろ」
いつも通りの行動=値切り交渉。である。物の価値が分かっているだけに「五万」とか口にするのは一種の拷問だが、これも仕方ない。安くて困る事は無いのは確かなのだし。
(サライス、今こそ、その演技力の全てを出し切る時よっ!)
サライスは結局、二割も値引いてしまった(六万で買った)。自身の行った所業に戦々恐々しつつ、店を出る。
(……あ、なんか今更、震えが)
良い買い物、というより極悪非道の限りを尽くした後のような感じ。生きた心地がしないとはこの事だろう。
数百万、下手したら一千万とかする代物である。それを六万で購入。……どんな詐欺だ。
だがしかし、最早気にしても仕方が無い事である。さっさと気持ちを切り替え(現実逃避とも言う)歩き出す。
「あ、いました。サライスさん!」
そこにかかる声。名を呼ばれたサライスは声の方を振り返る。
そこには金色の髪を肩の辺りで切りそろえ、セラスターン教団の修道士服を身にまとった少女がいた。
リィス・タリス。前回の仕事の護衛対象の一人だったのでサライスも良く覚えている。仕事の間は話をする機会はあまり無かったが。
ギルドでサライスが武器屋を探していたのを聞いてやって来たのだろう。
サライスに駆け寄るリィス。
……リィスは十七歳になる。サライスより年下なのだが、こうして並ぶとサライスの方が年下に見えるのが、なんとも物悲しい。
「何か用?」
「はい、レスター様が――」
「レスター? 高位神官の?」
それ以外に考えられないのだが、一応確認するサライス。
「はい、そうです」
サライスはそれに眉をしかめる。高位神官が特定の冒険者にギルドを通さずに用事。あまり良い想像はできない。
しかし、無視する訳にもいかないだろう。
「まぁ、分かったわ、用事も丁度終わったし案内して」
「はい」
サライスが通されたのは来客用の個室だった。そこには既にレスターが待ち構えていた。
「レスター様、サライスさんをお連れしました」
「ああ、助かったよ。いらっしゃい」
「ええ」
レスターの言葉にサライスは軽く返すと、勧められるままに椅子に腰掛ける。
レスターがリィスになりやら話しかけているが、サライスにその内容は聞き取れない。リィスがレスターに「分かりました」と一言残して退室する。
サライスはレスターが向かいの席に腰掛けるのを確認して口を開いた。
「で、なんの用があるの?」
「ああ、今回の仕事と関係があるのだけど」
それを聞いてサライスは若干表情を硬くする。レスターはそれに構わず言葉を続ける。
「君なら気づいていると思うから単刀直入に始めるけど、今回のアンデッドの発生は人為的なものである可能性が非常に高い。自然発生にしてはアンデッドの数が多すぎるし、何よりアンデッドスライムが紛れ込んでいた。アンデッドスライムは生息地が全く違うしね。何者かがあの遺跡に持ち込んだと考えたほうが自然だ」
「そうね」
レスターの言葉にサライスは一応は相打ちを打つが、レスターがなぜこんな話をサライスにするのかが理解できない。
「その人物が何を考えて、そんな事をしたのかは分からないけど、我々としてもこのまま放置しておく訳にはいかない、という事になってね。本格的に聖騎士団が動いて調査する事になった。今は遺跡の調査を行うための準備をしているよ」
「……それは良いけど、私に何をさせたいの?」
「本題はそこだね。遺跡の調査自体は聖騎士団が動くから良いとしても、もう一つ気になる事があってね。そっちの調査をお願いしたいんだよ」
「……調査?」
「そう、あの遺跡のアンデッド、どれだけの数がいたと思う?」
「さあ、……百、くらいはいたんじゃない」
自分が相手にしたアンデッドを脳裏に浮かべてサライスが答える。
「そう、百〜百二十体はいた。そうなると、そのアンデッドを作り出すための『死体』をどこから調達したのかが、また問題になってくる」
それだけの数の死体。となると、真っ当な方法で集められるものではない。
「……なるほどね。言いたい事は分かったわ。でも、なんで私? 正直、調査とかそういうのは苦手なんだけど」
「情報が全く無い訳でもない、ここ数年で国内で発生した失踪事件とかの情報は伝えるし、それに、君は“あの”リーベルト・ファルスの弟子なのだろ? なんとかなるんじゃないかな」
「……いつ気づいたの? 私が先生の弟子だって」
「君の名前を聞いた時だね。私の師と君の師は面識があってね。その関係で一度会った事があるんだよ。その時、君の名前が出たからね。名前を聞いた時、ピンときた」
「先生と同レベルの期待をされても困るんだけど」
「もちろん、そこまでは言ってないよ。……あまり、乗り気じゃないようだね」
「そりゃあね。そういう仕事は苦手だもの」
とは言え、サライスにもあの事件について調べてみたいという気持ちは少なからずあるし、仲間が殺された事に対する報復を犯人にしてやりたいとも思う。
が、やはり調査は苦手だ。
「まぁ、これは旅の片手間にでも調べてくれれば問題ないよ。それに、引き受けてくれれば、ギルドを通して定期的に報酬……というと変だけど、資金を送るし、調査の進行度とは関係なく、ね。だから、君にとって悪い事はないと思うよ?」
「何、その気味が悪いくらいの好条件は……」
「もちろん、それだけじゃなく、もう一つだけお願いがあるんだ」
サライスは「やっぱり」と内心嘆息した。そして、視線で先をうながした。
「実はリィスに旅をさせようと思っていてね」
「……は?」
「リィスは私の弟子みたいなものなんだけど、ちょっと世間知らずでね。教団出資の孤児院出身で、孤児院を出た後は直ぐに教団入りしちゃったものだから」
「……」
「で、旅に出して、世間というものを見せた方が良いだろう。と、思って冒険者ライセンスを取らせたまでは良かったんだけど、流石に一人で旅をさせるのは不安でねぇ」
なんだか、凄く過保護な事を言い始めたぞ、こいつ。と、サライスは思いはしたが言葉には出さなかった。
「……要するに、護衛をしろ、と?」
「いや、護衛というより、パーティー組んでくれない? 仲間……というよりは友人として付き合ってもらえると、とてもありがたい」
「それにしたって、なんで私」
「年齢も近いし、実力もある。では駄目かな」
サライスにはレスターの真意が計りきれず、小さく溜息を吐く。
「はぁ、分かったわ。今回の事件を調べてみたい気持ちが無い訳でもないし、……引き受けるわ」
定期的に資金が手に入るのは確かに悪い事ではない。パーティーを組む事も、絶対に嫌だと思っているわけでもない、客観的に見て断る理由の方が少ない。あえて言うなら、レスターの真意が計れないのが気分悪いくらいか。
「そうか、助かる」
そう言って笑顔を浮かべるレスター。
その表情を見ると、どうも、サライスには調査の方が建前でリィスの方が本題だったようは気がしてならない。
その後、戻ってきたリィスを交えて話が始まった。
「リィス君、準備は済んだかい?」
「はい、意味も分からず旅支度を済ませてきました。レスター様」
笑顔で言葉をつむぐリィスにレスターが冷や汗を流す。
レスターは咳払いをすると、一息に説明(別名、言い訳)を始める。サライスはそれを黙って見つめる。
(……本人、事後承諾?)
順序が有り得ない感じだが、目の前のやり取りを見る限り、そうとしか思えない。
「つまり、サライスさんと旅をして来い、という事ですね? レスター様」
「そ、そうなんだけど、いちいち語尾に“レスター様”ってつけないでくれる?」
レスターが語尾に小さく「怖いから」と言ったのをサライスは確かに聞いた。
「気にしないで下さい。レスター様」
微妙に、そう、注意していないと気づけない程度に“レスター様”の部分が強調されている。レスターはそれに気がついたのだろう。視線を逸らし咳払いをする。どうも、動揺すると咳払いをする癖があるようだ。
(……どうでも良いけど、弟子の方が立場強いわよね。これ)
サライスは自身の師弟関係とはまた趣きの異なる二人を若干新鮮な気持ちで見つめる。
「それはそうと、旅に出る事、それ自体は分かりました。サライスさんに同行する事にも私は異存ありません。サライスさんが納得なさっているのなら」
リィスが向ける視線に、サライスは無言で頷く事で納得している事を示す。そうしてからサライスは口を開いた。
「一つ聞きたいんだけど」
「あ、はい。なんでしょう」
「貴女はどのくらい戦えるの?」
一緒に行動するからには相手の戦闘能力をある程度認識しておく必要がある。サライスの質問はそういう思惑から出たものである。
そして、それに答えたのはリィスではなくレスターだった。
「一番得意としているのは、遠距離からの直射系射撃魔法による精密射撃。いわゆる“狙撃”だね」
「狙撃って……、聖職者が得意とする魔法には思えないわね」
「うぅ、気にしてるんですから言わないで下さい。第一、得意とか不得意とかは自分では選べないじゃないですか」
リィスの主張に「確かにね」とサライスは頷く。
特にセラスターン教団の人間が使う『ファーン』という魔法体系は得意と不得意がはっきり分かれる傾向が強い。
ファーンは精神力を魔力に変換し魔法に利用するため、術者の精神状態によって“扱える魔法が大きく異なる”。例えば怒りを感じている時と、冷静である時、この二つで使える魔法が異なってしまう。その為、戦闘などの自身の精神状態を意図的に操作するのが困難な状況下での安定性は最悪と言ってもいい。
そして、ファーンにおける『得意な魔法』は“軽い緊張を伴う、冷静な状態”で最も扱いやすい魔法である。リィスの場合、これが先ほどの『狙撃』にあたる。本人は甚だしく不本意な事ではあるのだが……。
精神力を魔力に変換しているため、消費魔力はとても低いのだが、敷居は高いと言える。更に専用の魔法杖が完全なオーダーメイドで高額なのも取っ付き難さに拍車をかけている。
ファーンを使いこなすと言う事は、『自身の精神を完全に制御し、使いたい魔法を最も効率よく使える精神状態を意図的に作り出せるようになる』事である。まぁ、こんなのは基本的に無理だ。
リィスが得意とするのが“狙撃”という、戦場から離れた場所で行使するものであったのは不幸中の幸いだったと言える。精神の制御が比較的容易だ。
「それじゃ、魔法以外はどう?」
「クウォータースタッフがちょっとだけ、くらいです」
クウォータースタッフというのは、長い棒状の打撃武器だ。リィスの扱う魔法杖は、その全長が180cmを超える。その魔法杖を打撃武器として使えば、結果としてクウォータースタッフの扱い方と同じようなものとなってしまう。
リィスの魔法杖の話が出たので、ついでにここで説明してしまうが、リィスの魔法杖は直射系の射撃魔法に最適化されており、この直射系射撃魔法を使う時に限り呪文を必要としない。そして、打撃武器としての使用も考慮して物理的衝撃にも頑丈な作りになっている。
「ちょっとだけ?」
「防御に専念するなら、まぁそこそこ。攻勢に出て敵を無力化するのはちょっと難しいかも、って感じです。元々、敵に近づかれた時の自衛用に覚えたので、あんまり」
「ああ、なるほどね」
魔法の得意分野が“狙撃”という事は近づかれた時の対応手段が無いという事だ。そのくらいの対策は講じていてしかるべきだろうと、サライスも納得する。
「さて、そろそろ私は席を外すよ。仕事もあるしね。……ああ、二人はまだ話していて構わないから」
レスターはそう言うと、二人が反応を返す前にさっさと立ち上がり退室していった。
「といっても、特に改まって話すような事もないし……」
「ですねぇ」
二人は苦笑しつつそう言葉を交わす。そして、サライスは椅子から立ち上がると口を開いた。
「まぁ、とりあえず、冒険者ギルドにいきましょう。パーティー登録くらいはしておいたほうがいいだろうし」
「あ、はい」
二人は連れ立って部屋から出た。
数十分後、リィスは冒険者ギルドのクラベンス支部にある、戦闘修練場に立っていた。あの後、話の流れでちょっと戦闘能力を実際に見ておこうという事になったのである。
流石に王都だけあって修練場の規模も大きい。リィスの射撃魔法を使うにも十分な大きさである。
「じゃ、適当に撃ってみて」
「え?」
「あ、的は私ね。適当に離れるから、ちょっと待って」
「あの?」
サライスはリィスの呼びかけに答えずさっさと離れていく。
リィスはどうやらサライスが本気らしい事に気づき、小さく溜息を吐いた。リィスは一応聖職者である。人に向かって攻撃魔法をぶっ放すのは好きではない。
(――でも、やらなきゃいけないんだろうなぁ)
リィスは少し遠い目をした。そして、サライスが十分離れた事を示すようにリィスに向かって手を振っているのが見える。
仕方が無いので、早く終わらせようとリィスは自分の身長を軽く超える長さを誇る魔法杖を構えた。
――来た。
サライスはリィスから放たれた魔力弾が一直線に自分に向かってくるのを感じると、防御魔法を無詠唱で展開。次いで一歩だけ横に動く。
サライスが展開した防御魔法はクリスタルに呪文を登録しているものだ。その為、無詠唱の割にはその防御能力は目を見張るものがある。少なくとも通常の緊急展開用防御魔法を超越した防御性能である。
しかし、その防御魔法による防御壁をリィスの魔力弾は貫通。一歩横にずれていたサライスの真横を通り過ぎる。
(……弾速、貫通性能、共に中々優秀、狙いも正確、流石に得意と言っているだけはある。と)
サライスが先日使った直射反射追尾弾の分裂バリエイションもそうだったが、基本的に魔力弾のように魔力そのものを対象にぶつけるタイプの攻撃魔法は威力が低い。
これは魔力が基本的に物理法則から逸脱しているのが原因だ。通常の状態の魔力では物理的な干渉はできない。だからこそ、普通は“発火”や“凍結”などの物理的な現象に魔力を変換する事で“副次的な結果として”破壊力を生み出すのである。
魔力弾は“発火”や“凍結”といった現象を省略していきなり破壊力を生み出す。これはとても効率が悪く、大きな破壊力を生み出そうと思ったらかなりの魔力を必要とする。
しかし、利点も存在する。それがリィスのような場合だ。リィスが得意とするのは『遠距離からの直射系射撃魔法による精密射撃』要するに精度が命である。この場合、魔力の物理的な干渉ができない、というのが利点に変わる。要するに魔力弾は空気抵抗や重力の影響を受けずに直進するのである。これは狙撃する事を考えるとかなりの利点だ。なにせ、空気抵抗や重力といったものの計算を全て省略できてしまうのだから。
そして、こういった魔力弾は破壊力よりも貫通性能を高める事が多い。消費魔力を多くするのではなく、魔力密度を高めるのである。例を挙げるなら太陽光とレンズの理屈が分かりやすいだろう。レンズを使って太陽光を一転に集中させれば火だって起こせる、そうでなくても紙に穴を開けるくらいの事は簡単にできる。
狙撃なんてものは基本的に連射するものでもない、対象の急所を一撃で射抜く。その性能が最も重要だ。広範囲を更地にするような破壊力は必要ない。
そう考えると、リィスの魔法はかなり優秀と言って良いだろう。
その後も、とにかくリィスの魔法の“程度”の確認を行い、旅立ちの日を決めて、この日は解散となった。
幕間一 【襲撃者と生存者と放浪者】 目次
分からない分からない分からない分からない分からない分からない。彼女には分からない。
――彼女の両親が倒れている。
分からない分からない分からない分からない分からない分からない。八歳になったばかりの彼女には分からない。
――彼女の周囲が一面“紅”で満たされている。
分からない分からない分からない分からない分からない分からない。カレンという名を持つ彼女には分からない。
――彼女には今、“人の死”を理解できるだけの思考能力は残っていない。
分からない分からない分からない分からない分からない分からない。なんの力も無い彼女には分からない。
――今、彼女は他者から与えられる強制的な死に直面していた。
分からない分からない分からない分からない分からない分からない。彼女には何一つとして分からない。
――彼女が気を失う直前に見たものは、銀色に煌めく――――――
カレン・インダ。彼女はある商人の一人娘である。つい最近八歳を迎えたばかりだった。
システ・ルタンがそこにやってきたのはただの偶然であった。五百年近く水の回廊に眠っていた彼女に知り合いなどいるはずもないので、目的地などありはしないのだ。
それでも彼女が旅に出た理由としては、一つに“そこに留まる理由がなかった事”、そして“旅を通じて今の世界(時代)を理解しようとした事”があげられる。
それと、できる事なら水の回廊の封印が消えた事による人間側の動向も知っておきたい。という思惑も彼女にはあったが、これはまず無理だろうと彼女は考えていた。現在の人間たちの勢力図を理解しないまま情報収集なんてのは、どだい無理がある。下手したら、彼女が魔法生命体だとかそんなのは抜きにして、不審人物として捕まる可能性すらある。
なので、彼女の旅に目的というものは存在しなかった。彼女は基本的に食事を必要としないし、その肉体から衣服に至るまでが魔力で構成されているので、資金稼ぎというものを考える必要もない。魔力が必要なら大気中の魔力を瞬時に支配下に置き、体内に取り込む事だってできるので、この時代の高位魔法生命体のように主人(あるいは他者)からの魔力供給も必要ない(そもそも、魔力を取り入れる必要すら殆どないのだが)。本当の意味でただ気軽に旅を続ける事ができた。
その彼女の所持品は水の回廊から持ち出したバスタードソードくらいのものだ。旅人としてはあまりに軽装。逆に目立ちそうだが、彼女はその事実に気づいていない。
彼女の持つバスタードソードは本来彼女の持ち物ではない。彼女が眠りにつく前、彼女に味方してくれた人間の愛用していた剣だ。懐かしさも手伝い、形見として持ってきたのである。彼女自身は剣なんて使えやしない。放置されていた期間の割には劣化が殆ど見られないのは状態固定魔法の恩恵でも得ていたためだろう。
バスタードソードはハンド・アンド・ア・ハーフ・ソード(片手半剣)に分類される剣で、両手剣と片手剣の中間に位置する剣だ。必要に応じて両手でも片手でも扱えるように作られている。腰に吊るすには少々大きすぎるので、システはこの剣を背に背負っている。
さて、前置きが長くなったが彼女がそこ――――商人の馬車が盗賊の集団に襲われている現場に出くわしたのはただの偶然だ。
システとしても面倒事は歓迎すべき事態ではない、彼らに気づかれる前にここを立ち去るべきだと考えた。ぱっと見、商人側に生き残りがいない事もこの考えを後押しした。
しかし、次の瞬間にはシステは走り出していた。そして――
一人の盗賊と、生き残っていた少女の間に割って入った。
システの長い銀色の髪が、少女の視界を埋め尽くした。
「姉ちゃん。こりゃ、なんのつもりだ?」
少女をその手の剣で斬り殺そうとしていた盗賊の男が不審気にシステに問う。
「……ただ、子供が殺されるのを黙って見ていられなかっただけです」
システは少女が殺されようとしているところを見て、動かずにはいられなかったのだ。彼女自身、そんな自分の行動をお人好しだと思わなくもないが、これも性格だ仕方がない。
彼女は基本的に人間を心から憎む事ができない。そういう風に“創られて”いる。システは良くも悪くも最高位の魔法生命体だ。その人格に至るまで完全に調整されていて、それが変質する事はまずありえない。
彼女が生を受けてから、人間からみたらそれこそ永遠に近い時間をすごす中で、数え切れないほど人間からの迫害は受けてきた。それでも彼女は人間を見捨てる事ができない。むしろ、自分と友好を結んでくれた人たちがいた事を嬉しく思う感情の方が強い。
だから、殺されかけている子供を見捨てる。なんていう選択肢は最初からなかった。
「なんだい、姉ちゃん。正義の味方か何かか? その背中の剣で俺たちを制裁するかい?」
男の馬鹿にしたような言葉に周囲の盗賊の男たちも笑い声を上げる。
システはこういった連中との議論が無駄である事を、長い人生の中で学んでいるので男たちに何を言うでもなく次の行動に移る。
システは自らの右腕を真横に突き出した。
それを疑問に思った男たちはシステを問い詰めようとしたが、男たちが口を開くより早くその異変は起きた。
視界を埋め尽くす白、白、白、白。
男たちの目が強烈な光に焼かれ、視界が白で埋め尽くされる。
「うわっ!」
「な、なんだ!?」
「どうなってやがる!!」
音も熱もない。ただ、強烈な光だけがある。その光は発生から数秒で、発生した時と同様に唐突に消えた。
しかし、男たちの目はそうは行かない。視界が回復するのにそれから数分を要した。
視界が回復した男たちが最初に見たのは、異変の直前と同様、右腕を真横に突き出したシステの姿。
次に男たちが見たのはシステの腕が示す方向にあるもの。それを見た男たちは一様に顔色を変えた。
そこには森と表現するといささか誇張に過ぎるが、それでもそれなりの木々が茂っていた。その木々の一部――――数にすると五本程度だろうか、それが地面ごと消失していた。
男たちはシステが何をしたのか瞬時に理解――いや、何をしたのかは理解はできなくても“それ”を成したのがシステである事は明白であったため、言葉を発する事もなくその表情に恐怖を貼り付ける。
システはそんな男たちを黙って見、ついで、その右腕を男たちに向けた。
そこに至って、男たちは弾かれた様に行動を開始する。
あるものは制止の声を上げ、あるものは許しを請い、あるものは逃げ出した。
それから数分。システは黙って男たちを見ていただけだが、男たちの姿はもはやこの場になかった。
システはもう近くに盗賊たちがいない事を確認すると、ため息を吐いて頭に手を当てた。
「痛っ」
力を使ってから軽い頭痛と吐き気がする。
システはその力を人間に対して使えないように、自身に封印をかけている。対象が人間でないなら先ほどのように力を使う事が可能だ。
しかし、この封印はかなり強力なものだ。盗賊たちに向けた敵意に反応して頭痛などの症状を引き起こしたりもするのだ。
「はぁ、とにかくはったりが通用して良かった」
システは魔力運用に特化した魔法生命体だ。その能力は「魔力を操り制御する事」。魔法に似た能力であるが、“人間の魔法”と“システの能力”はその次元が大きく異なる。システが人間の魔法を模倣する事はできるが、人間がシステの能力を模倣する事はできない。それだけ、システの能力が人間の理解を超えているという事だ。しかし、それに比べ身体能力は人間のそれと大差ない。盗賊たちが襲い掛かっていたら力を封じているシステには打つ手はなかった。
自身のはったりが上手くいった事に安堵しつつ、システは周囲をゆっくりと見回す。そして、自分が助けた少女で視線を止める。
「どうも、この子以外に生き残りはいないみたいね……」
気を失っている少女を見ながらシステは呟いた。
第五話 【対面無き邂逅】 目次
「なんじゃこりゃ」
そこを見た時のサライスの第一声はこれだった。
そこにはほぼ無傷の馬車があった。――それは良い。問題はその周囲に複数の人の死体が転がっている事だ。
馬車の馬も死んで――いや、はっきり言おう。殺されている。
死んでいる人間は数や服装から見るに、馬車の持ち主とその護衛、と言ったところか。
「うーん……」
サライスは困ったように呻くと、横目にリィスを見る。――顔色が悪い。
アンデット討伐に比べれば見ず知らずの人間の死体が転がっている事くらいは大した事ではない。とサライスなんかは思うのだが、それを口にしたところでリィスの同意は得られそうにない。
「ふぅ」
流石に放置する訳にもいかないので、無駄だろうと思いつつも生き残りがいないか確かめてみたが、やはり生き残りはいない。あるいは既にこの場から逃げ出しているのかも知れないが。
ちなみに、グラストは現在この辺り一帯を見回り中である。まだこれをやった輩が付近にいる事を考えての行動だ。
「これは、順当なところで盗賊の仕業かなぁ」
サライスは結論を口にするが、どうも自分が出した結論に自信を持てていない風だ。
「どうしたんですか?」
リィスはサライスの煮え切らない口調に気づき尋ねる。
「いや、盗賊って割には物が持ち出された形跡がないしな、と思って。盗賊じゃないなら、……怨恨か」
「……怨恨ですか、あの、魔物の仕業とかは考えられないんですか?」
「なに? 聖職者としては怨恨とかは考えたくない?」
小さく笑いつつサライスが問い返す。
「え、いえ、そういう訳じゃ」
「まぁいいけど、多分、魔物って線はないわよ。ここは人通りが少ないっていっても街道だし、魔物なんて早々現れないわ。それと、死体の傷が重量のある刃物によるものが殆どである事と、魔物にやられたんだとしたら死体が綺麗すぎるのも理由としてはあるけど」
サライスは付け加えるように「まぁ、刃物云々はあまり当てにならないけどね……」と小さく呟く。
魔物には人型のものもいれば、ある程度知性が高いものもいる。当然、武器を扱う事のできる魔物も存在する。武器による傷ばかりだからと言ってそれイコール“魔物の仕業ではない”という事にはならない。まぁ、人間がやった可能性の方が高いのは確かだが。
その為、今は後者の“死体が綺麗すぎる”という部分が重要となってくる。
「……綺麗?」
“死体が綺麗すぎる”という言葉の意味を理解し切れなかったのかリィスが問い返す。
「そ、魔物にやられたんだったら、普通その死体はどこかしら欠損してるもんだし、場合によっちゃ死体自体残らないわ」
「……」
サライスの言葉の意味するところを理解したリィスはその顔色を急速に青くする。
死体の欠損。死体が残らない。というのは要するに“喰われる”という事だ。無論、全ての魔物が人を喰う訳ではないが、いくら魔物でも人を襲うには相応の理由が必要だ。その理由で最も多いのはやはり“食事”だ。なので魔物に殺されればその死体は大抵欠損している。
「んな訳で、怨恨、要するに“殺す事”それ自体が目的だったんじゃないかと思ったんだけど、これも、わざわざ他人に目撃されかねない街道で護衛付きの人間を襲うかな、と考えると疑問なのよねぇ」
「それで盗賊ですか」
「自信はないけどね。襲ったは良いけど何か不測の事態が発生して物も盗らずに逃走、って考えれば一応の筋は通るし」
「……」
「で、その不測に事態には“あれ”が関係している可能性が高い、と」
と、サライスが視線を向けたのは、木々が茂っている一角。恐らくはそこにも木が生えていただろう位置、そこの地面が綺麗にえぐれて――いや、“消えて”いた。
――――サライスたちが今いる場所はつい数時間前までシステがいた場所だ。
「どうだった?」
周辺の見回りから戻ってきたグラストに対するサライスの問いかけだ。
【ふむ、こちらに向かってくる盗賊らしき集団ならいたな。“これ”の犯人かは分からんが、目的地がどこであろうとここにやってくるのは確かだろうな】
「うん?」
その集団が“これ”の犯人だった場合、ここに戻ってくる理由はなんなのか、そこにサライスは疑問を感じた。
「……人数は?」
【約二十】
「多いわね」
となると、不測の事態によってこの場を退散したものの現場に残してきた“物品”が惜しくなり、“不測の事態”の事もあって数を揃えて舞い戻ってきた。これが可能性としては高く思える。
サライスとしては盗賊の集団が“偶然ここにやってくる”なんて考えられないのだ。
そういえば、とサライスは思う。この地方には賞金がかけられた盗賊団が活動しているとギルドから伝えられていたのを思い出す。グラストが目撃した集団が“それ”なのかは分からないが。
冒険者は基本的にギルドに“これからどこに行くのか”を伝えておく事が習慣付いている。これは冒険者がどこにどれだけいるのかをギルドが把握していれば仕事の斡旋がしやすいという背景がある。仕事の斡旋もそうだが、今回のサライスのように、これから向かう地方の情報もギルドからある程度は提供されるので、冒険者側としても利点の方が多い行動である。そのため、定着しやすい習慣ではあった。
「あの、どうしたんですか?」
グラストの言葉を理解する事ができないために置いてきぼりを食らっているリィスがサライスに尋ねる。
それに、サライスが状況を説明する。
「盗賊ですか」
「そう。……で、私としてはさっさとここから退散する事をお勧めする」
【……まぁ、現実的ではあるな】
グラストはサライスの言葉に同意する。が、リィスは違った。
「それって、この人たちをほったらかしにして逃げるって事ですか!?」
死体を放置したまま逃げるというのは、聖職者としては同意できない事項なのだろう。
憤慨した様子のリィスを見てサライスは冷静に口を開く。
「そうは言ってもね。今回の場合“殺人”だから私たちが勝手に死体を埋葬したりって事はできないのよ? できるのは然るべき場所にこの事を伝える事だけ。まぁ、状態固定魔法で死体の腐敗を防止するくらいはしても良いけど」
サライスたちの場合、然るべき場所というと冒険者ギルドが妥当なところだ。冒険者ギルドに伝えれば、そこから各方面に情報が行き適切な処理がなされる。
「それに、私たちがこの場に残って、盗賊連中と戦って、結果として勝ったとしても、数が多すぎて私たちだけじゃ連行とかはできやしないわ。結局、相手を野放しにするしかないのよ? ここに残る理由が何一つないわよ」
「そ、それは……、でもっ」
「納得できない」リィスの表情は明らかにそう言っていた。
それを見てサライスは溜息を吐く。サライスとしてもリィスを加えた現在のメンバーでの実戦を早い段階で経験しておきたい、という思いはあるのだが、それにしたって盗賊二十人は多すぎる。
これが遭遇戦だったならともかく、相手が来るのが分かっているのに戦う事を選ぶのは、馬鹿げた選択だとしか思えない。
思えないのだが、サライスはもう一度溜息を吐くとグラストに向かって口を開いた。
「連中の装備はどんなんだった?」
【……見た感じでは、ポールアックスやクレセントアックスなどの竿状武器が中心に見えたが、……小さな装備に関しては流石に確認できなかったからな、あまり当てにならん。魔法使いの有無も分からんしな】
(うわっ、戦いたくない……)
サライスはどう戦うかを考え始める。リィスを交えた初めての実戦なのだから、サライスが魔法で一掃するという方法は正直あまり意味のある行動ではない。それなら戦わない方はましである。
この戦闘に意味を見出すとすれば二つだ。一つはリィスを交えた実戦の経験、それにサライスの新しい剣“リジェダル”の使い勝手を確かめる事くらいだ。双方とも訓練という意味ではそれなりにやっているがやはり実戦とは異なる。
なので、戦闘をするなら先の二つに関して意味のあるものにしたいところだ。
しかし、そうなると戦法は限られてくる。特にサライスは片手剣であるリジェダルで戦う事になる訳だから、間合いの広いポールウェポンとの戦闘は難しいものがある。“戦いたくない”と思うのも仕方ないところだ。
「はぁ、まぁいいわ。手っ取り早く作戦を決めましょう。やるからには勝たないと」
「え?」
「……戦うんでしょ?」
「あ、はい!」
【……身内に甘い気質はマスター譲りか】
「う、うるさいわね……」
結局、リィスの意見を優先していたりするのでサライスも強く否定はできなかった。
それは、先生との模擬戦が修行の一環となったある日の事だった。
「お前は戦闘で最も重要なのはなんだと思う?」
先生はそんな問いを私に投げかけてきた。
「戦闘で一番重要な事……ですか?」
「そうだ」
戦闘に必要な要素なんてものは、それこそ膨大にあるもので当時の私にはその中から“一番重要な要素”を選別するのはかなり難しいものだったが、先生に質問された以上は答えなければならなかった。
私は考えた、私も先生も基本的に魔法使いだ。通常の戦士などとはまた違った視点を持つ必要があるだろう。それに加え先生は“知識の大魔法使い”と呼ばれるような人だ。……となると、正解は?
今にして思うと、“正解を探してる”時点で駄目駄目だったのだが、その時の私はとにかく正解を探していた。その結果たどり着いた答えは。
「……知識、ですか?」
実に魔法使い的な答えだと当時の私は思ったものだ。しかしながら、それに対する先生の反応は薄かった。
「そうか」
一言呟き沈黙。……って、先生?
「あの、先生?」
「ん? なんだ?」
「正解は?」
「正解?」
先生は“何を言ってるんだこいつ”という表情をした。先生、私は一生忘れませんよ、その表情。
「正解なぞあるはずなかろう。何を重視するかなんてものは個人によって違うものだ。もちろん、私とお前とでも違ってくる」
「え、じゃあ、なんであんな質問を?」
「今後の教育方針の参考にするだけだ。……まぁ、お前が知識が重要だと認識している事は分かったからな、今後はしばらく座学に重点を置く事になるだろうな」
「え゛」
座学? 正直に言おう。私は座学が苦手だ。ひょっとしなくても墓穴を掘ったみたいだ。
抗議しようかとも思ったが先生は一度決めると弟子である私の言葉なぞに聞く耳持たないので、抗議するだけ無駄である。
私は暗澹たる思いで現実を受け止める事とした。そして、先生に一つだけ質問を投げかけた。
「先生が戦闘で重要だと思っている事ってなんですか?」
「私か? 私が一番重視しているのは――――」
(――――“演技力、次いで観察力”って先生、あの時は自分の聴覚に疑問を持ちましたよ)
サライスは木陰に隠れ盗賊がやってくるのを待ちながら過去を回想していた。リィスとグラストは別の場所に潜伏しているのでこの場にはサライスしかいない。
演技力と観察力。確かに必要な要素の一つであるとは思える。が、戦闘において“一番重要か”と聞かれたら、なんとなく首を捻りたくなるのは仕方のないところだろう。
サライスの師が言うには『演技によって相手の思考を誘導し戦闘を優位にする事が可能』らしい。そして、適切な演技をするには相応の観察力も必要だという。
サライスも師の演技力がすごいと言う事は理解している。何せ何年も続けた模擬戦ではサライスは常に「もう少し強くなれば一撃入れられるかも」と“思わされ続けた”。その事に気がつくのに年単位で時間がかかったのはサライスとしては悔しい所である。
そうこうするうちに、盗賊連中が現場にやってくるのが見えてきた。
今回の戦闘の作戦は単純だ。まず、遠距離から(と言ってもそれほど離れている訳ではないが)リィスの射撃魔法で奇襲、敵がリィスの方に気を取られたのを確認してサライスが別方向から襲撃、相手が浮き足立っている内に数を減らす。グラストは念のためリィスの護衛として置いてあるが、状況に応じて独自に動く事となっている。
これだけで二十人を全て倒すのは、まぁ、まず無理だ。その後は臨機応変に対応するしかない。相手が引いていくならそれで良し、場合によってはこちらが敗走する事も視野に入れねばならない。
“やるからには勝たないと”。これは先ほどのサライスの言葉だ。当然、目指す先は“勝利”である。しかし、だからといって勝ちに拘って怪我をする必要はどこにもない。特に今回はどうしても勝たなければいけないような状況でもない。敗走を視野に入れるのは当然である。
そんな訳で、サライスは身を隠して襲撃のタイミングを計るために盗賊たちの様子をうかがっている。
すると馬車に近づく盗賊たちの姿が見えた。
サライスが「そろそろか……」と思った数瞬後、盗賊の一人が転んだ。リィスの射撃魔法が足に命中した結果だ。威力が抑えられているので実害は殆どないが、注意を引くには十分だろう。
が、盗賊たちは「ただ転んだ」としか認識してくれなかった。
(……気づきなさいよ!)
転んだ盗賊をからかうような声がかすかに聞こえる。それを聞きながらサライスは内心悪態をつく。
転んだ本人も首をかしげているものの、事態に気づく気配はない。
次いで、立て続けに二人の盗賊が転んだ。リィスも相手の鈍感さに多少あせったようだ。
……が、結果は同じであった。転んだのは「本人がドジだったから」で片付けられてしまった。
(えーと…………)
これはもう、襲撃をかけるべきかとサライスは一瞬考えたが、行動に起こす事なく傍観に徹する。この後、リィスがどう行動するか興味があったのだ。
その結果はサライスの予想をある意味で上回るものだった。
それほど待つ事無くそれは起きた。馬車の周りに集まる盗賊。吹き飛ぶ馬車の車輪。吹き飛んだ車輪の直撃を受け倒れる一人の盗賊。車輪を失い倒れた馬車の下敷きになる盗賊二人。……一瞬のうちに三人の盗賊が行動不能である。これをやったリィスにしても、予想以上の事態であっただろうと思われる。
(おー……)
一言で言うなら「すげぇ」という感じ。
ともかく、襲撃をかけるなら今である。盗賊たちの注意が馬車に集中している今を逃すのは勿体無い。
サライスは予め鞘から引き抜いていたリジェダルを片手に物陰を飛び出すと、一気に加速し盗賊らに接近した。
盗賊の一人がサライスに気がつき、慌てて自らの武器を構えようとするが間に合わない。
当然、サライスはそれに構わずリジェダルを一閃。相手のポールアックスと呼ばれる武器を“真っ二つに斬り飛ばし”、返す刀でその手首を斬り付ける。それほど深い傷という訳でもないが、武器を振るうのは無理があるだろう。
「――なぁっ!?」
驚きの声。これは手首を斬られた事よりも、むしろ“武器を切断された”事に対する驚きだろう。
(知識では知ってたけど、切れ味良すぎ。手ごたえ全くないから、逆に体勢崩しそうになったわ)
リジェダルのような武器の基本的な使い方の一つに『刀身に魔力刃を展開して振るう』というものがある。今、サライスがやったのはこれだ。今は明るいから分からないが、暗闇の中ならリジェダルの刀身が淡く光っている事が確認できただろう。
魔力刃は総じて“切れ味が異常に鋭い”(正確には術者がその切れ味を任意に設定できる。サライスの場合、戦闘中に切れ味を微調整するなんていう芸当はできないので最初から切れ味を最大に設定している)。その為、武器の切断なんて芸当が可能なのだ。
この異常な切れ味のおかげで、物を斬った手ごたえは殆どない。今まで普通の剣を使ってきたサライスにすれば勝手の違うところだ。
だが、サライスには「今まで使ってなかったから使わない」なんて考えはない。使えるならば使うべきなのだ。
実際、武器を破壊して無力化するという目的を達するには、かなり有効な手段でもあった。
――――これがサライスが選んだ相手を殺さずに無力化する方法だ。“武器を破壊し、武器を振るう腕を斬る”これにより戦闘力を奪うというものだ。完全な無力化とまでは流石に言えないが、相手を殺さないという事を考えれば有効な手段だと言えるだろう。
他にも足を攻撃し機動力を奪うというのも考えとしてはあったのだが、これは今回の場合はよろしくない。機動力を奪えば“相手は逃げられなくなる”、これでは困るのだ。相手が逃げるなら逃げてくれた方がサライスとしてはありがたい。そうである以上、機動力を奪うというのは選択肢から外れてしまう。
サライスは、たった今斬りつけた盗賊を蹴り倒すと、他の盗賊に向かった。
突然の馬車の倒壊と、それに続く襲撃により盗賊たちの混乱は未だに収まっていない。この機にできる限り多くの相手を無力化したいところだ。
サライスが向かった先にいるのは二人。これを先ほどと同じ要領で倒す。混乱に乗じての事だったので、それほど困難な事ではなかった。
これで計六人を戦闘不能にした計算だ。
この時点で、この場にいる盗賊連中のリーダー格の男が流石に我に返り、声を張り上げた。
「何してやがるっ! そんな小娘に梃子摺ってるんじゃねぇ!!」
その大喝に正気づいた数人の男がサライスを包囲するように動き始める。
(チッ、余計な事を)
流石に、ここから先は簡単にいきそうにない。
早速、サライスから見て正面に位置する男が長剣片手に突っ込んでくる。この一撃をサライスは刀身の側面を上手く使って受け流す。――刃の部分で受け止めると、その異常な切れ味でもって切断された長剣の刀身がサライスに向かってすっ飛んでくる危険大なので、こんな神経を使う作業が必要なのである。……切れ味が良すぎるのも問題アリだ。
サライスは攻撃を受け流されて体勢を崩した男を足払いで地に倒すと、今まで同様その男を戦闘不能に――するような余裕は流石に無く、別方向から迫る男達に対処する。対多人数戦闘は忙しいのである。
(あー、うざいっ!)
これが、相手を問答無用で殺して良いのならいくらでもやりようはあるのだが――ぶっちゃけ魔法で一掃とか。
まぁ、サライスの中では、どうしようもないようなら魔法という手段も選択肢にあったりする。自分が死ぬより相手に死んでもらった方が良いに決まっている。運が良ければ死なないし。
それでも殺さないに越した事は無いので、大勢の敵を相手にしつつ、ちまちまと隙を見つけては地道に相手を戦闘不能に追い込んでいく。
そんな感じで何とか二人ほど戦闘不能にした時、サライスが敵の攻撃を回避し体勢が硬直したところに、丁度良いタイミングでクレセントアックスが振り下ろされる(偶然か狙ったのか分からんが、ただ、どっちかと言うと偶然臭い)。
(ちょ、それは待って……っ!)
まぁ、待つはずも無いし、待ってくれようとしたとしても、既に落下運動を開始している大重量のクレセントアックスを止めるなんて芸当が出来る人間、そうはいない。少なくとも、そこらの盗賊には出来ないだろう。
サライスも特に、そんな事は期待していなかったようで既に次の行動に移っていた。が、回避運動直後の体勢では攻撃を受け流すのは少々無理があるし、まともな回避運動も間に合いそうも無い。
そこでサライスがとった行動は、足の力を抜き転倒、転倒の勢いそのままに地を転がる。という、とにかくその場から移動というものだった。結果、クレセントアックスは地面を抉るにとどまった。
が、問題はこの後である。この時、サライスは後の事なぞ考えずに攻撃の回避を優先していた。地面を転がり、その運動エネルギーを無駄にしない綺麗な立ち上がりを披露した直後、その表情は引き攣った。サライスの現在の立ち位置は“敵のど真ん中”である。何処を向いても馬鹿っぽい(←サライスの主観である)男どもの顔、顔、顔。非常にまずい。
サライスの後頭部には当然、目なんて物は存在しないので、この状況ではどうしても死角が生まれる。流石のサライスも、この状況で無傷でいられると思えるほどには己に自信を持ってはいない。
ついでに言うと、以前の剣より若干重たいリジェダルを振り回していた右腕も、ちょっぴりヤバイ。割とピンチである。
盗賊たちは思った。
――――獲った!
サライスは思った。
――――殺るか?(←魔法で)
……どっちかと言うと、盗賊の方がピンチかも知れなかった。
とは言え、呪文詠唱とかやってる余裕はないので、結局、剣で戦う事になる。まぁ、魔法を使おうと思えばやりようはあるのだが、この状況下からの魔法発動までの労力を考えると、このまま剣で戦った方が面倒がない。
クリスタルを使えば無詠唱で防御魔法も使えるので、死ぬような事態には早々ならないだろう。
それらの状況を思考でではなく、感覚で感じたサライスは手近の男の急接近する。それこそ長剣の間合いよりも遥かに短い距離まで敵の懐に潜り込むと、左手で短剣を引き抜き、敵の腕を切り裂く。男はサライスがそこまで接近してくるとは思っていなかったらしく、咄嗟に行動を起こす事もできずに得物を取り落とし腕をおさえる。
サライスはリジェダルとは違う人を斬る確かな手ごたえを感じつつ、その男の脇を抜けるようにして包囲の突破を試みる。
しかし、流石にそう上手くも行かず、サライスの進行方向を塞ぐ形で一人の男が立ちふさがり、その手の長剣を振り下ろす。前進の慣性から回避は難しいと考えたサライスは、咄嗟にリジェダルでその長剣を受け流そうとする。
「――ッ!」
しかし、今までリジェダルを振り回していた疲労からか、右腕の反応が遅れた。これでは攻撃を受け流す事は到底無理だ。
それでもサライスはその攻撃を何とか受け止めて見せる。
「――くっ、そ」
受け流す事のできなかった衝撃に、サライスの足がその場に縫い止められる。
「良し! そのまま抑えとけ!」
その声に反応してかは分からないが、地面に押さえ付けるように力が増す。サライスは短剣を放して、空いた左手でリジェダルの刀身を支え、片膝をついて何とかこれに耐える。
しかし、サライスは眼前の男とは別の男が武器を手にこちらに近づくのを察知した。これには流石に冷や汗が流れる。
(……これは、仕方ないか)
こうなってしまうと最早選択肢は無い。サライスは懐のクリスタルに意識を向ける。
相手の攻撃を防御魔法で防ぎ、その隙に窮地を脱する。という方法くらいしか、今のサライスには打つ手が残されていない。
サライスは近づいてきた男が武器を振り上げる気配に合わせて、懐のクリスタルに魔力を集中、防御魔法の発動のタイミングを計った。
「これで終わりだぁっ!!」
ご丁寧に声を上げてくれるのでタイミングが計りやすい。
しかし、サライスが防御魔法を発動する事はなかった。そして、攻撃がサライスに当る事もまた、なかった。
「……え」
サライスにも周囲の盗賊達にも一瞬何が起きたのか分からず、彼らは皆呆けた。分かるのは男の攻撃がサライスではなく地面をとらえたという事だけだ。
その中で最初に行動を再開したのは、やはりと言うべきかサライスであった。
状況の把握を後回しにしたサライスは、クリスタルに集中しかけていた魔力を霧散させ、同じくクリスタルに向いていた意識を瞬時に引っ張り戻すとまず、自らを押さえ付ける男の長剣を脇に逸らし、ついでとばかりに足払いをかける。
「なっ、うわぁ!」
転倒する男に構わず、サライスは盗賊達の間を縫うようにして抜けると、十分な距離を置いて再度、連中と対峙した。流石に放した短剣の回収までする余裕はなかったので、それは放置した。
(さて……何が起きたの?)
若干の余裕ができたサライスは状況の整理を始める。流石に動きを封じられていたサライスに対する攻撃が外れるのは、状況的におかしい。
「お、お前っ! 何を遊んでやがる!?」
「え、いや、遊んでるわけじゃなく、なんか光の玉みたいなのが当って!」
「あんだそりゃっ!?」
サライスは男達の問答を聞いてピンときた。
(……リィスかっ!)
正直、サライスは自分の事に手一杯でリィスの存在をすっかり忘れていた。
恐らく、魔力弾をぶつける事で攻撃の軌道を逸らしたのだろう。
そうすると、サライスが思っていた以上にリィスは実力者という事になる。少なくとも精密射撃という面においては、サライスを上回るだろう。
(さて、でもこれ以上戦うのは体力的に無理があるわね。ここまできて魔法に頼るのも何かしゃくだし)
現状が把握できたなら、次に行なうはこの状況の打破だ。
今のサライスは握力的にリジェダルを振り回すのは難しい。前に使っていた剣に比べて重たいのは理解していたつもりだが、思いのほか限界がくるのが早かった。先のピンチはこれが原因と言えるだろう。
剣の重量に関しては対策が必要だとサライスは頭の片隅に留める。
それを踏まえた上で、現状を打破するとしたら。
サライスは未だに揉めている男達を見る。
(今なら上手くすれば逃げられなくもなさそうだけど……)
現在のグラストの現在位置も考えに組み込みつつ、思考を巡らす。
(できるなら、相手に引いてもらうのが理想だし……そうね、後ははったりでなんとか……)
既に十人弱を戦闘不能に追い込んでいるので、殊更余裕がある要に見せれば引いてくれるだろう。という判断だ。まぁ、演技力次第という感じだ。
(……よし)
短い思考の後、方針を決定。リーダー格の男に向かって口を開く。
「ねぇ、引く気はある?」
「何だと?」
「引くんなら追わないわよ」
「はっ、小娘一人に何故俺たちが引かないとならない?」
「あら……」
サライスは殊更ビックリした様子を見せる。
「その小娘一人に随分被害を出してるじゃない、引いた方が賢明だと思うけど」
「ふん、俺たちに勝てるなら“引け”なんて提案そもそもしねぇだろうが」
「えぇ、私一人じゃ勝てないわね」
そのサライスの返答に男は怪訝な表情をする。
「でも、タダでやられてやる筋合いはないからね。……これ以上被害を出してまで手に入れないといけない物が、この場にあるとは思えないのだけどね」
「む……」
ここで、サライスは無邪気とも言える笑顔を見せていった。
「ところで、どうして私が一人だ。なんて判断したの?」
「な、……に?」
「私一人じゃ、確かに貴方達全員に勝つのは無理だけどね。前提として“そもそも私は一人じゃない”のよ? 正直、負ける気しないわ」
「……はったりだな。仲間がいるのに何故一人で戦う」
それを聞いてサライスは思わず笑みを浮かべる。
「別に、私は一人で戦ってなんかいないわよ? 要所で仲間の援護は受けていたわ」
「何だと?」
「最初の馬車のあれも、私に対する攻撃を逸らしたのも、私の仲間の仕事だしね」
「何っ、どうやって。……まさか」
「ま、仲間の中には魔法使いもいるって事ね」
実際に魔法を使って見せた訳ではないので、自分が魔法使いである事は伏せる。
「……」
「さて――」
サライスは再度、男に尋ねた。
「――引く気、ある?」
サライス、盗賊達が去るのを見送り息を吐いた。
「……ありえないくらい疲れた」
【全く、少し無茶が過ぎないか?】
グラストが街道の脇、木々の間から姿を見せつつ言ってきた。
「どうにかなったんだから、別に良いじゃない」
【奴らが引かなかったらどうするつもりだったんだ?】
「別に、そういう状況になれば魔法も使っただろうし、グラストも出てきただろうし、どうとでもなったんじゃない?」
【……楽観的な】
「起きなかった事について、あれこれ考えたってしょうがないわよ。それよりリィスは?」
防御魔法があったとはいえ礼くらいは言うべきだろう。と思い所在を尋ねる。
【少し遠くに隠れてるからな、まぁ直ぐ出てくるだろう】
「そう」
サライスは駆け寄ってくるリィスを見ながら思った。
(……先生、“演技力”って重要ですね)
